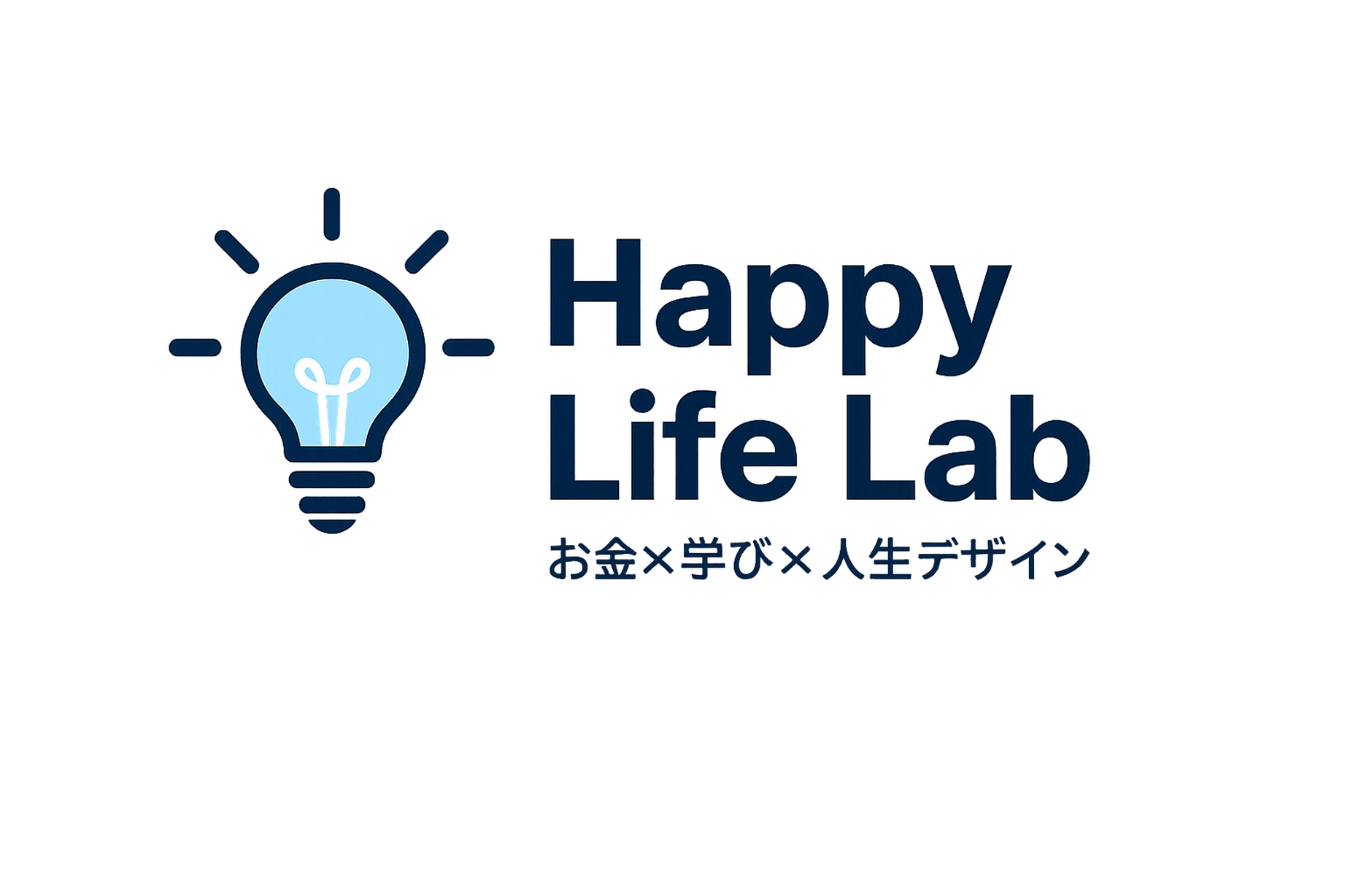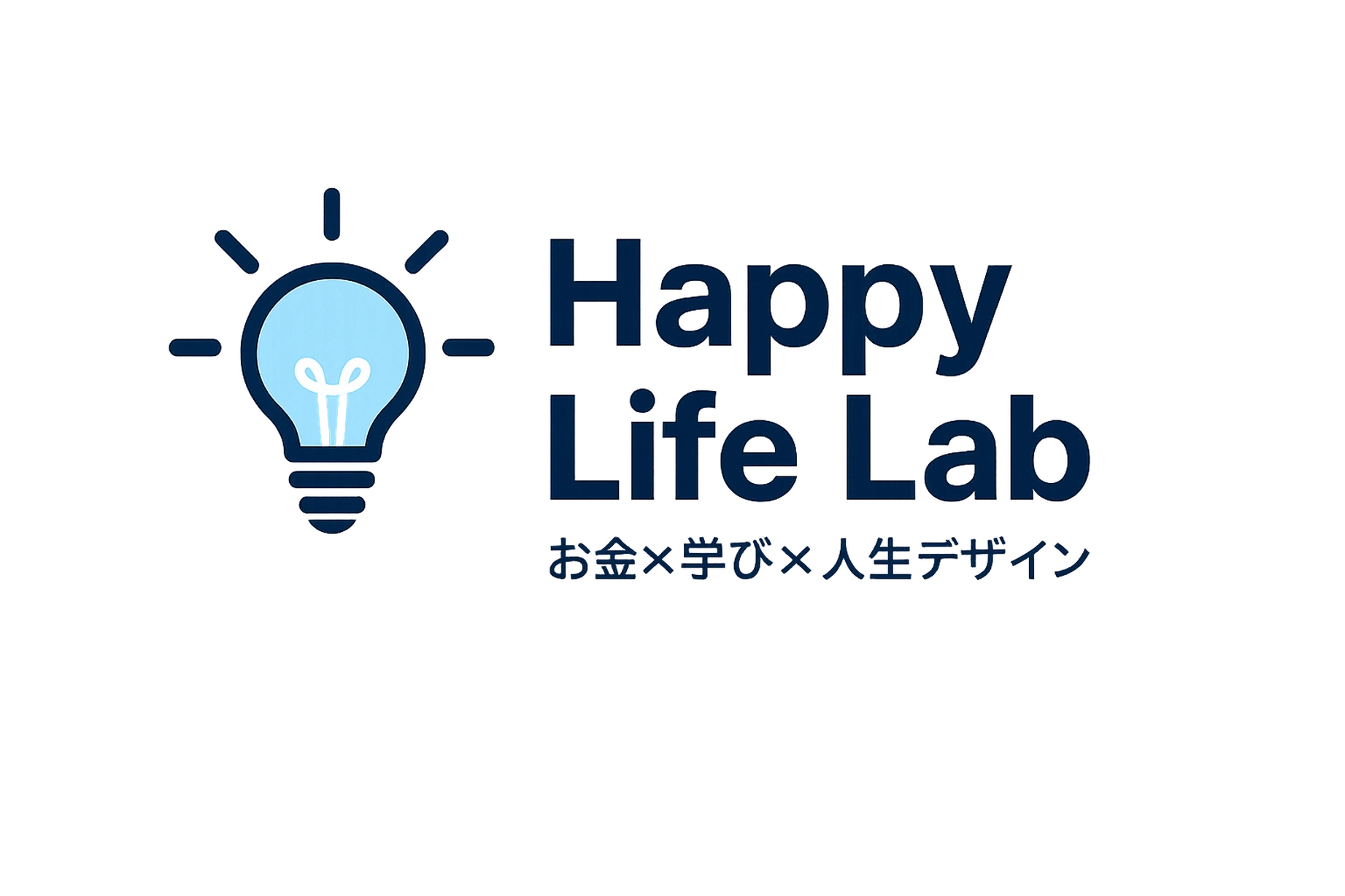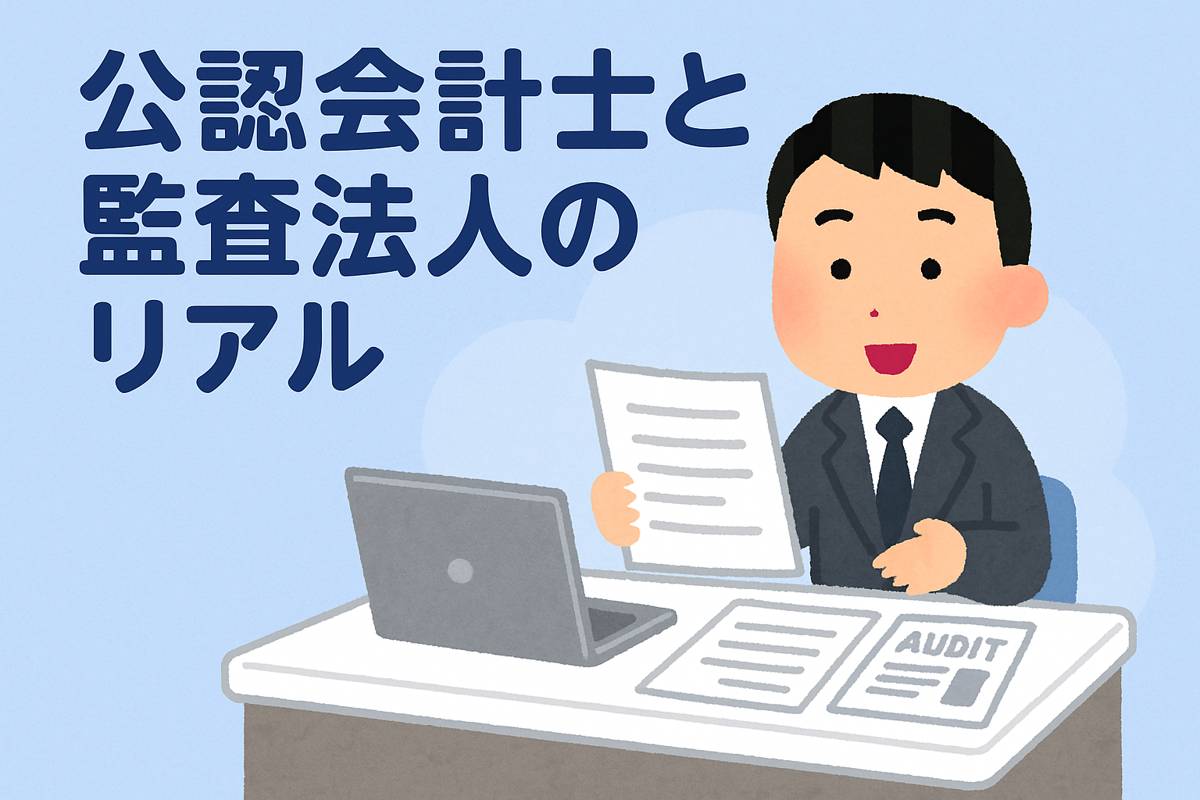公認会計士と監査法人のリアル|「監査って何?」をわかりやすく解説
こんにちは、公認会計士のJOYです。このシリーズ「監査のトリセツ」では、監査の世界を15回にわたってわかりやすく解説していきます。初回のテーマは「公認会計士と監査法人のリアル」。公認会計士という専門職の裏側を、実体験も交えてお話しします。
監査って何のためにあるの?
「監査」と聞くと、なんだか堅苦しい印象を持つ人が多いかもしれません。でも、監査は経済社会の信頼を支える“見えないインフラ”です。
企業が発表する財務諸表(決算書)は、株主や投資家、銀行、取引先など、多くの利害関係者にとっての判断材料。その数字が正しいかどうかを独立した第三者の立場で確認し、「適正です」とお墨付きを与えるのが公認会計士による監査です。特に上場企業や上場をしていなくても一定以上の会社規模の会社については、社会的な影響が大きいなどの観点から公認会計士による監査が法律で義務付けられています。
つまり監査とは、「企業と社会の信頼の橋渡し」をする仕事。言い換えれば、資本主義の裏方として“信頼の品質保証”を行う職業だともいえます。
公認会計士とは? 税理士・コンサルとの違い
公認会計士は、会計・監査・経営のプロフェッショナルであり、国家資格の中でも最難関の一つであり、正式に定められているわけではありませんが、医師、弁護士、公認会計士が国家三大資格と呼ばれることがあります。よく比較されるのが税理士や経営コンサルタントですが、それぞれの役割は異なります。また、公認会計士や弁護士は、税理士の国家試験を受けることなく、税理士登録をすることが可能となっています。
| 職業 | 主な役割 | 独占業務 |
|---|---|---|
| 公認会計士 | 監査・会計・経営アドバイス | 財務諸表監査 |
| 税理士 | 税務申告・税務相談 | 税務代理・申告書作成 |
| 経営コンサルタント | 経営改善・戦略立案 | なし(自由業) |
つまり公認会計士は「企業が作った決算書をチェックする唯一の資格」。税理士やコンサルが“作る側”だとすれば、会計士は“検証する側”です。
監査法人とは? チームで動くプロ集団
会計士の多くが所属する職場が「監査法人」です。監査法人は、一人で仕事をこなすのではなく、チーム制で動くプロフェッショナル集団です。監査法人はチームで働く集団であるため、チーム内で役割に応じて働くことが求められます。また、チーム制を取ることにより何重にもチェックを行うため、監査法人で働いた経験を有する会計士がチェック体制のない事業会社などに行くと恐怖を覚えるというのはちょっとした小話です。私もダブルチェック体制が最低限ない環境で働くのは今でも慣れません。チーム内には、結構変な人が紛れ込むこともあります。そうなると、ちょっと面倒ですよねー。
法人の種類は大きく分けて規模別に次の4タイプがあります。
- Big4(4大監査法人):トーマツ、あずさ、EY新日本、PwCあらた。大規模上場企業やグローバル企業を中心に担当。現場で最先端の監査の経験を積みやすい環境。
- 準大手・中堅法人:IPO準備企業や中堅上場企業を中心に実務。現場経験を積みやすい環境。
- 中小監査法人・個人事務所:比較的小規模な上場企業や学校法人などを対象に地域密着型で監査を実施。新人を取ることはまれで他で経験を積んだ会計士が多い環境。
監査は、特に大手の監査法人では、パートナー(責任者)・マネージャー・シニア・スタッフといった多層構造で進められ、全員で「適正意見」を導き出すチームワークが求められます。中堅以下の監査法人では、大手の監査法人で多様な経験を積んだ非常勤のスタッフ公認会計士が多く、彼らの果たす役割が重要であることもあります。
監査の現場:地味だけど、実はクリエイティブ
監査の現場では、数字をチェックするだけでなく、その背後にあるビジネスの実態を見抜く力が必要です。
「この売上はいつ認識すべきか?」「この資産の評価は妥当か?」といった判断には、会計基準だけでなく業界理解も欠かせません。当然ながら会社特有の事情などの情報も踏まえたうえで、今はこのような会計処理を採用しているが、その会計処理で問題ないかということを確認する必要があるのです。そのため、会計基準等の知識、業界の知識、会社固有の情報に関する知識の3つの知識を備えないと監査を行って会社の会計処理の適否を判断することはできないのです。必ずしも絶対にコレが正しい処理と言い切れない場合もあり、クライアントとの議論を通じて、最適な会計処理を導くこともあります。
つまり監査は、数字と経営の“対話”です。地味に見えて、実はかなり知的で創造的な仕事なのです。
監査法人で働く日常とキャリア
会計士の働き方は季節で大きく変わります。3月決算企業の監査繁忙期(4〜5月)は朝から晩までクライアント先でデータ検証。体力と集中力の勝負です。朝は会社の始業時間より少し後にクライアントに伺い、夜は終電で帰れば良い方だったみたいな時代もありました。タクシー帰りで自宅に朝5時に着いて、風呂入って寝て8時に起きて、クライアントに9時半には着いているみたいな生活をしたこともあります。昨今は、労働基準監督署が厳しいため、さすがにこのような状況にはなく、スタッフであれば夜9時、10時には遅くとも帰るという話を聞いたことがあります。
一方でオフシーズンは、比較的自由に時間を使えるのも特徴。勉強、副業、転職準備など、自分の時間を確保しやすい時期です。ただし、これは大手監査法人の国内監査部門であればの話になります。国際部門やIPO部門などは変則決算が多く、私が在籍していたIPO部門などは、変則決算だらけのため、毎月どこかの自分の担当クライアントの決算があり、年中期末監査を実施しているということもあります。
監査法人で経験を積んだ会計士は、その後さまざまな道へ進みます。
- 企業の経理・財務部門へ転職
- コンサルティングファームでM&Aや内部統制支援
- ベンチャー企業のCFO(財務責任者)
- フリーランス会計士として独立
- 教育・研究職として大学や専門学校で活躍
監査法人での経験は「会計のプロ」としての信頼を得る基盤になります。特に、大手の監査法人は過酷ですが、色々な経験ができると思います。最近は、自己監査になるため、会社の資料を作ることはありませんが、以前は、会社に資料を作ることがない場合には会計士がドラフトを作ると言うことも当然になされていました。このように、資料を検査するのみにあらず、ドラフトを作るような経験もできるため、作る側と検査する側の両方を経験できることからコンサルタントとしても即戦力として働くことができたり、企業の側で即戦力として資料を作ることができるケースが多かったのではないかと思います。
ただし、もちろん、今はこのようなことはできないと聞いています(笑)
まとめ:信頼を支える“縁の下の力持ち”
監査の仕事は派手ではありませんが、社会の信頼を支える要です。会計士の一言が、上場企業の信用を左右することもあります。
数字の裏にある「企業の実像」を見抜き、健全な経済を支える——。
それが公認会計士という職業の本質です。
昨今、IPO企業の粉飾が監査法人によって見逃されているなどの報道も多く、この点は憂慮されますが、監査法人に強制捜査権がなく、クライアントから報酬をもらっており、意図的に監査法人や会計士を欺こうとする不正会計に対しては、現行制度上の公認会計士や監査法人に限界があるようには思います。
個人的には、ワールドワイドで上場会社については投資家から源泉税を徴収し、その一部を会計士制度に充当し、監査対象からの報酬で監査を行うというプロレスのような構造は止めるべきではないかと思います。そうでないと、自らを『市場の番人』とは言えないでしょう。