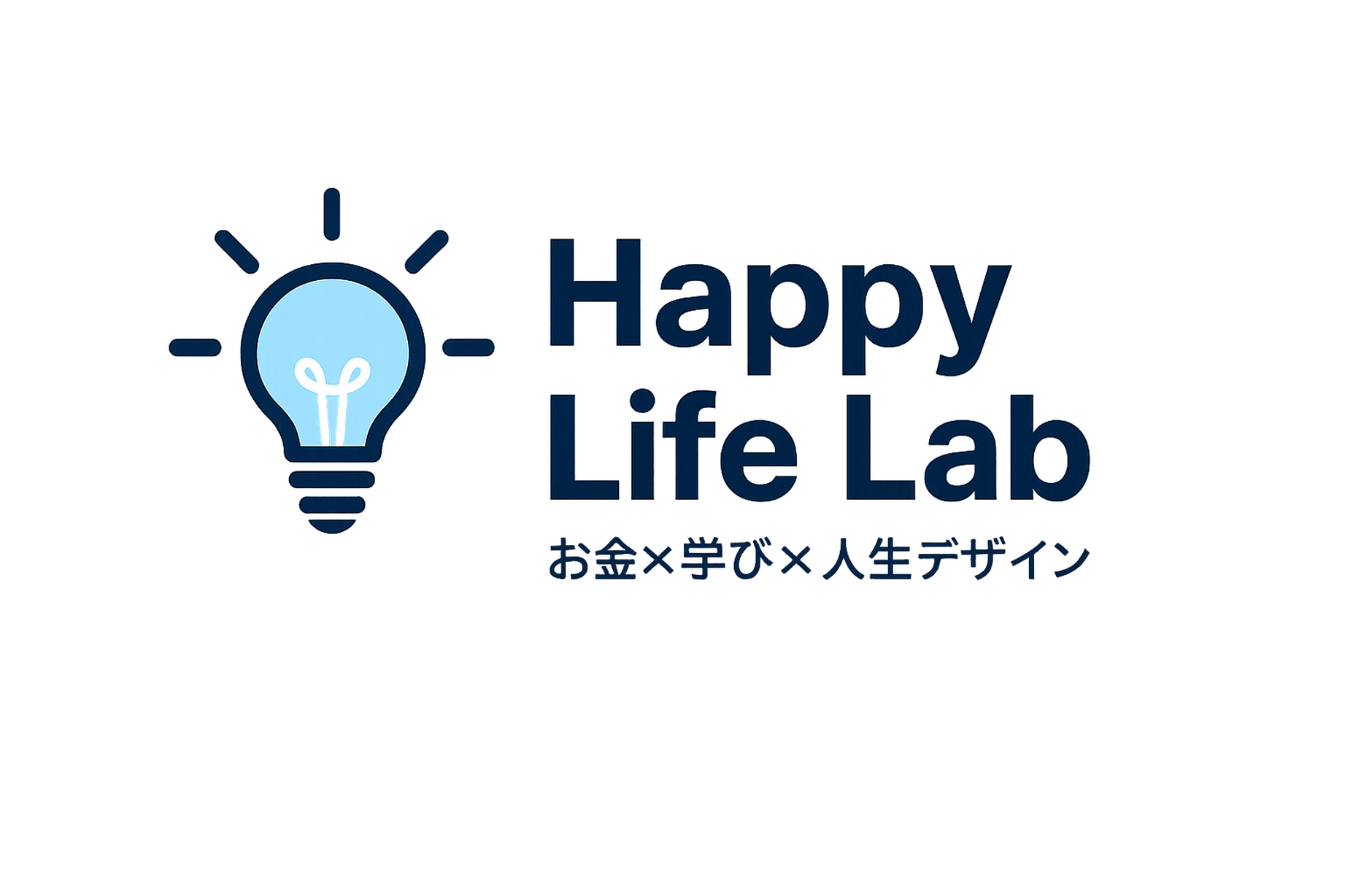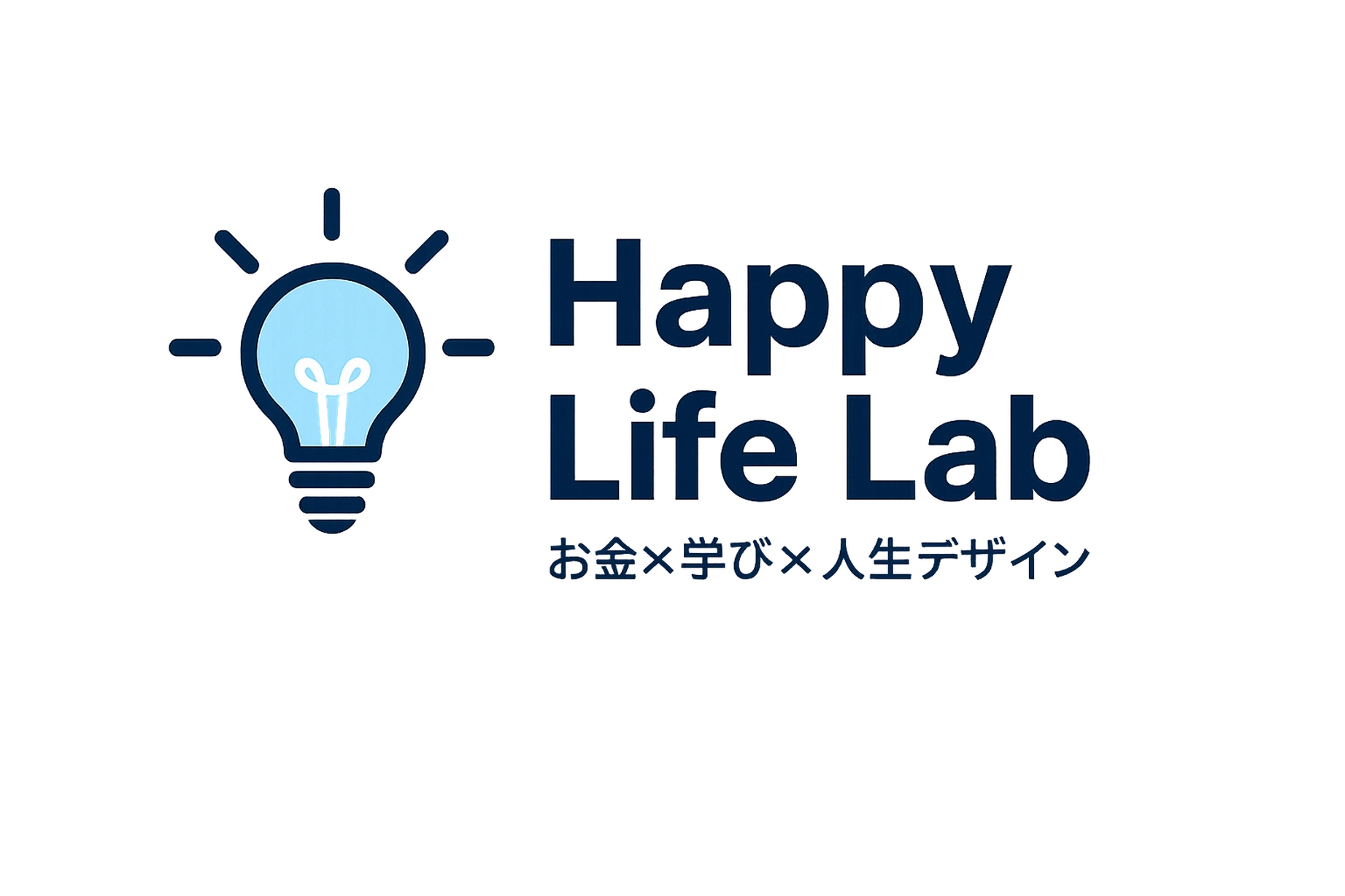IPO監査のトリセツ|IPOの基本とメリット・デメリット
IPOとは何か・なぜ目指すのか|上場の意義と最新動向
IPO監査のトリセツ
① IPOの基本とメリット
1. はじめに
企業がIPO(株式公開)を目指すのは単なる資金調達にとどまりません。IPOは「社会的な信任を得る通過儀礼」であり、企業にとって大きな成長ステージに進むための一歩といえます。近年、日本では年間80〜120社前後が新規上場を果たしています。コロナ禍で停滞した2020年前後から回復傾向にあります。
ただしIPOは華やかなイメージとは裏腹に、企業に重い義務とコストを課す仕組みでもあります。本稿の前半では、まずIPOの基本と主なメリットを解説し、最近のIPO動向を事例とともに紹介します。
________________________________________
2. IPOの基本的な仕組み
IPO(Initial Public Offering)とは、これまで一部の株主しか持っていなかった株式を証券取引所を通じて広く一般の投資家に公開することを意味します。
東京証券取引所にはプライム市場・スタンダード市場・グロース市場の3区分があり、企業規模や成長段階に応じて選択されます。たとえば、既にグローバル規模で事業を展開する大企業はプライム市場を目指しますが、ベンチャー企業やスタートアップはグロース市場に上場し、成長資金を調達するのが一般的です。
IPOを達成すると、株式を新たに発行して多額の資金を市場から直接調達できるようになります。同時に、株価という客観的な市場評価が常に突きつけられることになり、企業活動の透明性・説明責任が一層強まります。
________________________________________
3. 上場のメリット
(1) 資金調達力の強化
IPO最大の魅力は、市場を通じて幅広い投資家から直接資金を集められることです。未上場の間は銀行融資やベンチャーキャピタルへの依存度が高く、条件交渉に縛られるケースが多いですが、上場後は資本市場という開かれた舞台で資金を調達できます。
たとえば2023年4月に上場した楽天銀行は、IPOで700億円以上の調達に成功しました。この資金をデジタル金融インフラ拡充に活用し、個人顧客向けだけでなく法人向けサービス強化も計画しています。IPOによって成長投資を一気に加速させた代表例といえます。
(2) 知名度・信用力の向上
IPOは単にお金を集めるだけでなく「社会的信用を得る」ための強力な手段です。証券取引所の厳格な審査を通過すること自体が、ガバナンス・財務の健全性を外部に証明する行為となります。
東京プロマーケットなどで、アジアに展開する企業などが、IPOを機にブランド力を高め、国内外からの信用を獲得し事業を有利に展開するケースもあります。上場による社会的信用がグローバル展開を後押しするようなケースもあるということです。
(3) 株主・社員へのメリット
IPOは既存株主にとって資産の流動性を高める機会でもあります。創業者が一部株式を売却して資金を得ることが可能になり、ベンチャーキャピタルは投資回収の出口戦略を実現できます。
また、社員にとってはストックオプションの価値が現実の資産価値に変わる瞬間でもあります。IPOを経て株価が安定すると、従業員の士気や採用力が向上し、結果として企業全体の競争力が強まります。IPO前とIPO後では求人を行った時の応募層が明らかに異なり、IPOを契機に高学歴の人材の応募が大幅に増加したなどという話を聞くことがあります。IPO前の人材とIPO後の人材で軋轢が生まれるなどということがもちろんあり得ますが、IPO前の人材はストックオプションなどを通じて一定の経済的な利益を得ていることが多く、軋轢を生むことなく転職などを通じて人材の流動化を図るということも可能となります。オーナー社長が、自分の持っている不動産への抵当権を外すことができるというのも大きなメリットになりますよね。これは、実際にこの点を目的としているわけではないですが、オーナーが喜んでいるところを頻繁に見る部分ではあります。
(4) 制度・税務面での利点
上場企業は開示・統治を前提としているため、政府や自治体による補助金・優遇制度の対象になりやすい側面があります。特に「税制適格ストックオプション」や「研究開発減税」は代表的です。IPOによって資本市場からの資金調達と制度面での後押しを同時に享受できるのです。
________________________________________
4. 最近のIPO動向と事例
ここ数年の日本のIPO市場は「二極化」が顕著です。大型案件では楽天銀行のように700億円以上の大きな規模の調達が行われる一方、中小規模のスタートアップがグロース市場で数十億円規模の資金を確保する例も多く見られます。
近年は特に社会的に意義がある業種については、IPOが成功し易い傾向にあるように感じており、IPOを果たし、社会課題解決型ビジネスが市場に評価される傾向が強まっているように思われます。
________________________________________
5. IPOの基本とメリットのまとめ
IPOは「資金調達」「知名度・信用力」「人材確保」「税制・制度利用」といった多面的なメリットを企業にもたらします。近年の事例を見ると、規模の大小を問わず、IPOを契機に事業成長を一気に加速させているケースが数多く存在します。
ただし、IPOは華やかな舞台に立つことと同時に、後半で触れるような「重いデメリット」も背負うことを意味します。IPOを検討する経営者は、その両面を冷静に見極める必要があるでしょう。
上場後に直面するリスク・コストと意思決定フレーム
② IPOのデメリットと判断軸
1. はじめに
IPOには大きなメリットがある一方で、必ずしも「すべての企業にとって最適解」とは限りません。むしろ上場後の維持コストや外部株主からのプレッシャーによって、経営が思うように進まなくなるケースも少なくありません。ここでは、IPOの代表的なデメリットを解説し、企業がIPOを目指すかどうかを判断するための軸を整理します。
________________________________________
2. IPOの主なデメリット
(1) 持株比率の低下と経営権リスク
IPOに際して新規株式を発行すると、創業者や既存株主の持分比率は必ず低下します。大株主であるベンチャーキャピタルや機関投資家の影響力が強まると、創業者が望んだ経営方針を実行できないリスクも生じます。特に成長戦略を巡って「短期的利益を求める株主」と「長期的ビジョンを重視する経営陣」の間で対立が生じることは珍しくありません。
創業者が株主を中心とした「市場対応」に追われ、本来注力すべき新規事業開発に時間を割けなくなった事例もあるように思います。
(2) 継続的な開示・IRコスト
上場企業には、四半期ごとの決算短信、有価証券報告書、適時開示など、数多くの開示義務が課せられます。これらを作成・開示するためには財務経理・法務・IR部門の強化が不可欠であり、社内リソースを大幅に割く必要があります。
ですが、創業経営者は、利益を生まない間接部門に対して大きな意義を見出すことができないことが多く、IPO後しばらくの間は間接部門は脆弱であるケースが多いことから間接部門に大きな負荷がかかり人材の入れ替えが激しく、企業内部に開示やIRに関する知財が蓄積しずらくかえってコストだけを招くというケースが散見されます。。
(3) 上場維持コストの重さ
IPOは「一度上場すれば終わり」ではなく、維持コストが毎年発生します。上場料・監査報酬・システム投資・コンプライアンス対応費用など、その総額は中小規模の企業にとって決して軽くありません。
監査報酬や間接部門で多額に発生する内部人材コスト等は未上場企業には発生しないコストであり、資金繰りに余裕がない企業にとっては重荷になり得ます。
(4) 経営の短期志向化
株式市場は四半期ごとの業績に強い関心を持つため、上場企業はどうしても短期的な数値目標を意識せざるを得ません。これにより、本来は数年単位で進めるべき研究開発や新規市場開拓が後回しになるリスクがあります。
実際、米国の一部テック企業では「株価対策として自社株買いを優先し、研究開発費を抑制した結果、競争力が低下した」例が報告されています。日本でも同様に、IPO後に株価を意識しすぎて長期戦略が犠牲になるケースもあると思われます。
(5) 情報公開による競合リスク
IPOに伴い、詳細な財務情報や経営戦略を開示する必要があります。これは投資家保護の観点では必須ですが、同時に競合企業にとって貴重な情報源にもなります。利益率の推移や研究開発の方向性が公になることで、競合に対策を打たれやすくなるのです。
________________________________________
3. IPOを目指すべきか?判断軸の整理
IPOを選ぶべきか否かは、単に「資金が必要かどうか」ではなく、企業の成長戦略や文化に照らして総合的に判断する必要があります。
(1) 企業の成長ステージ
• スタートアップで「一気に市場シェアを拡大したい」場合 → IPOによる大量調達は有効。
• ニッチ市場で安定収益を上げている企業 → 必ずしもIPOは不要。未上場のままオーナーシップを維持する道もある。
(2) 経営者のビジョンと株主構成
• 長期的に独自路線を歩みたい経営者 → 外部株主の介入に耐えられるか?
• VCやPEファンドが既に大株主の場合 → IPOは出口戦略として求められることが多い。
(3) 業種・事業モデル
• IT、バイオ、インフラなど巨額投資が不可欠な業種 → IPOが成長の加速装置になる可能性が高い。
• 労働集約型の小売やサービス業 → 上場維持コストの方が重くのしかかる場合もある。
(4) 海外展開の有無
• 海外投資家を巻き込みたい場合、IPOは効果的な資金調達手段。
• 国内市場中心なら、地道な銀行融資や私募債で十分なこともある。
________________________________________
4. IPOのデメリットのまとめ・学びのポイント
• IPOのデメリットは「持株比率低下」「開示・維持コスト」「短期志向化」「競合への情報流出」など多岐にわたる。
• 判断の基準は「成長戦略にIPOが本当に必要かどうか」。
• IPOはゴールではなくスタートであり、上場後の経営体制・株主対応・ガバナンスが問われる。
まずは、「自社がIPOを選ぶ理由は本当に資金調達だけか?」を考えてみてほしいと思います。IPOの舞台に立つことは大きなチャンスであると同時に、長期的な覚悟と準備が不可欠なのです。経営者が躊躇半端な覚悟でIPOを目指すことにより、従業員に大きな負荷がかかったり、事業が傾いたりということもあり得るような大きな負荷がIPOにおいてはかかるものです。IPOをして、利益を出すために事業上の不正をしたり、会計不正を行うということになってしまった場合には、IPOしたということがそもそも大きな失敗ということになります。
IPOの監査を行ううえでも、経営者がきちんと覚悟を持ってIPOを目指すに至っているかをしっかりと見極める必要があり、覚悟ができておらず中途半端な気持ちでIPOを目指している社長が経営する会社のリスクは高いと思われます。私はこれまでに覚悟が足りていないかなーという経営者を大勢見てきた気がします。
IPOは10社中1社成功すれば良いくらいに言われていますが、大手の監査法人が受けてくれるような優良会社でそのくらいの確率より若干低いくらいかなというのが私の経験的な認識です。実際にはIPOを目指す会社全体で見るともっと確率低いと思いますので、やはり経営者に絶対の覚悟が必要ではないかと思います。