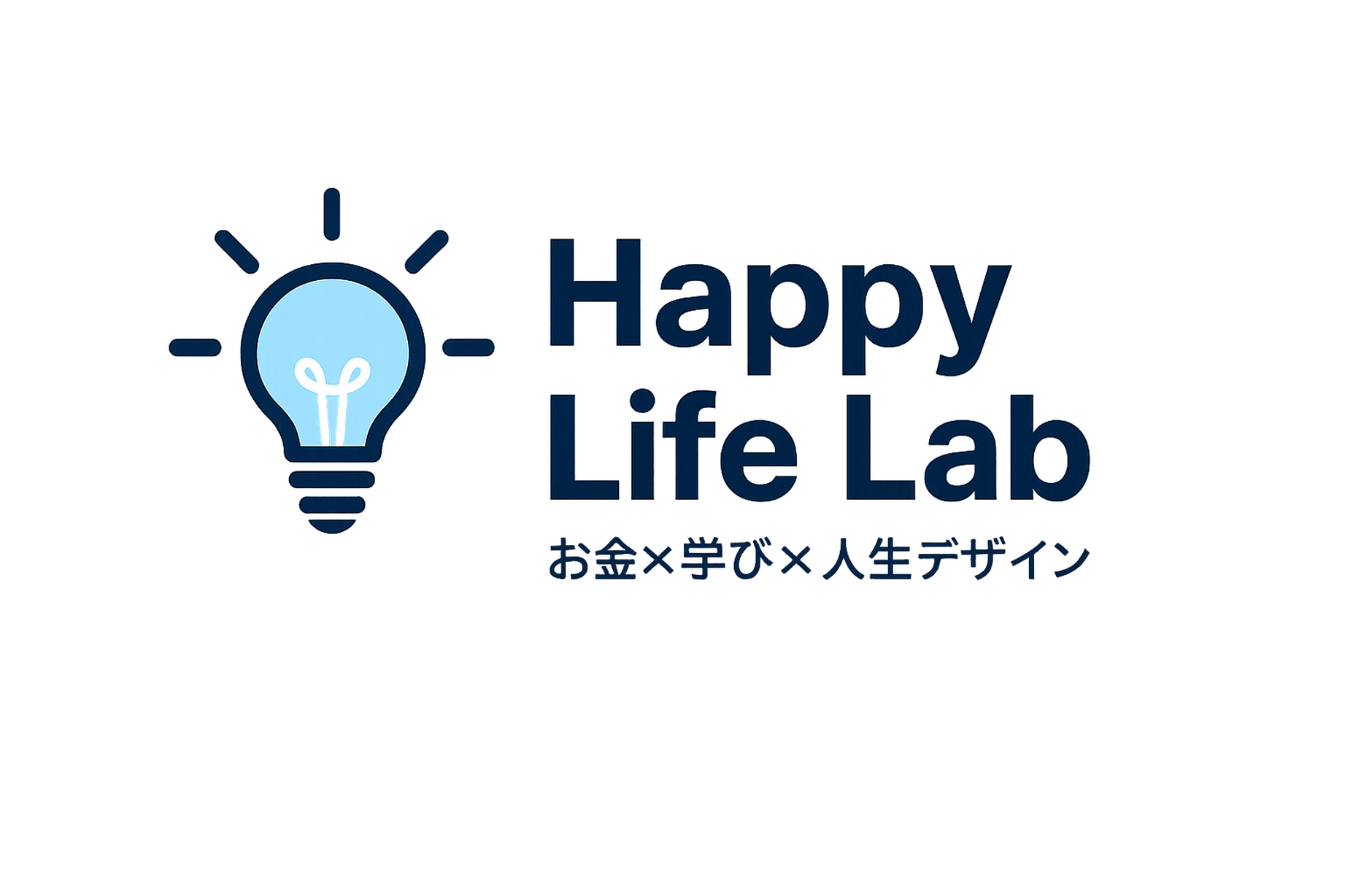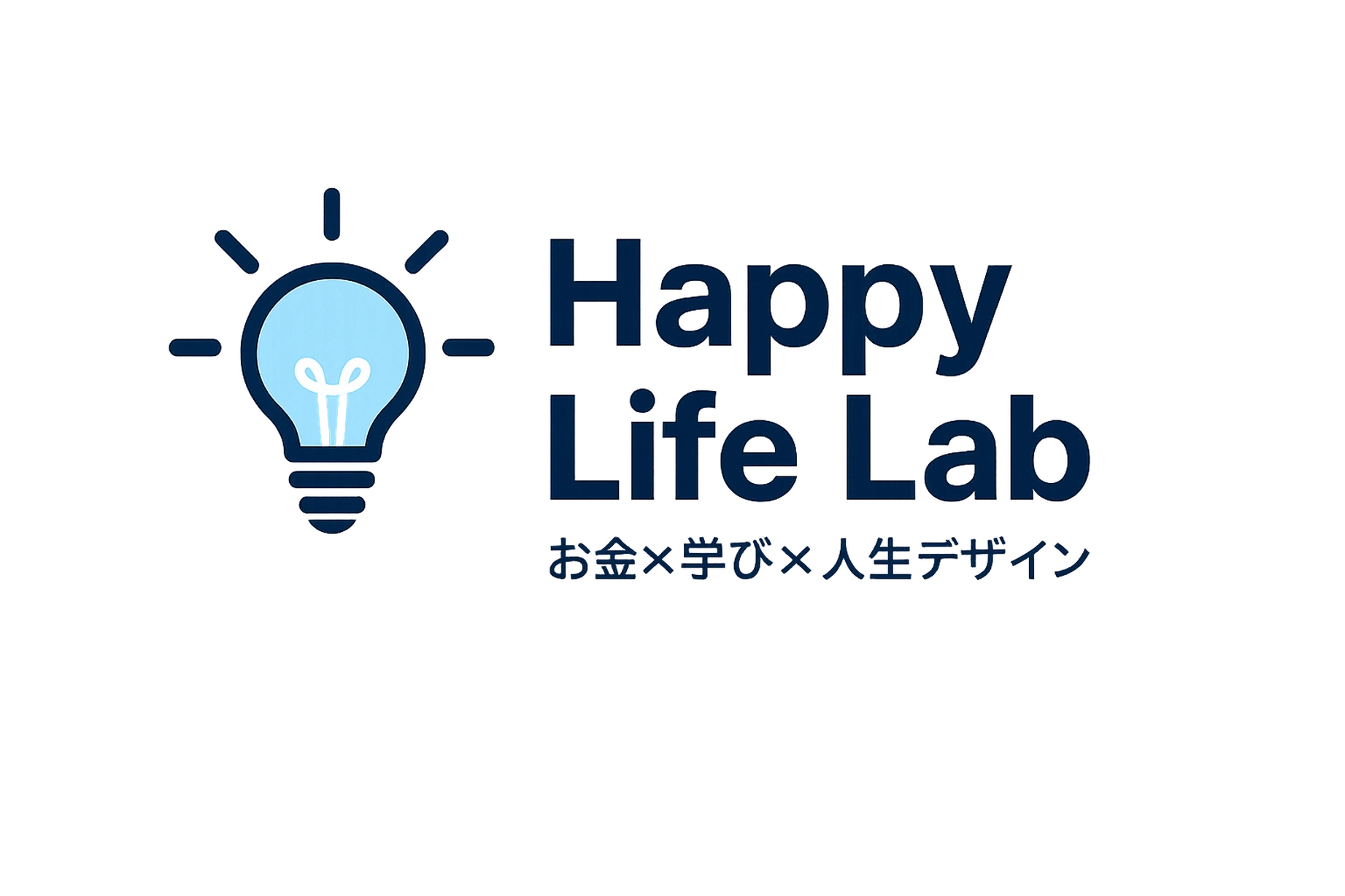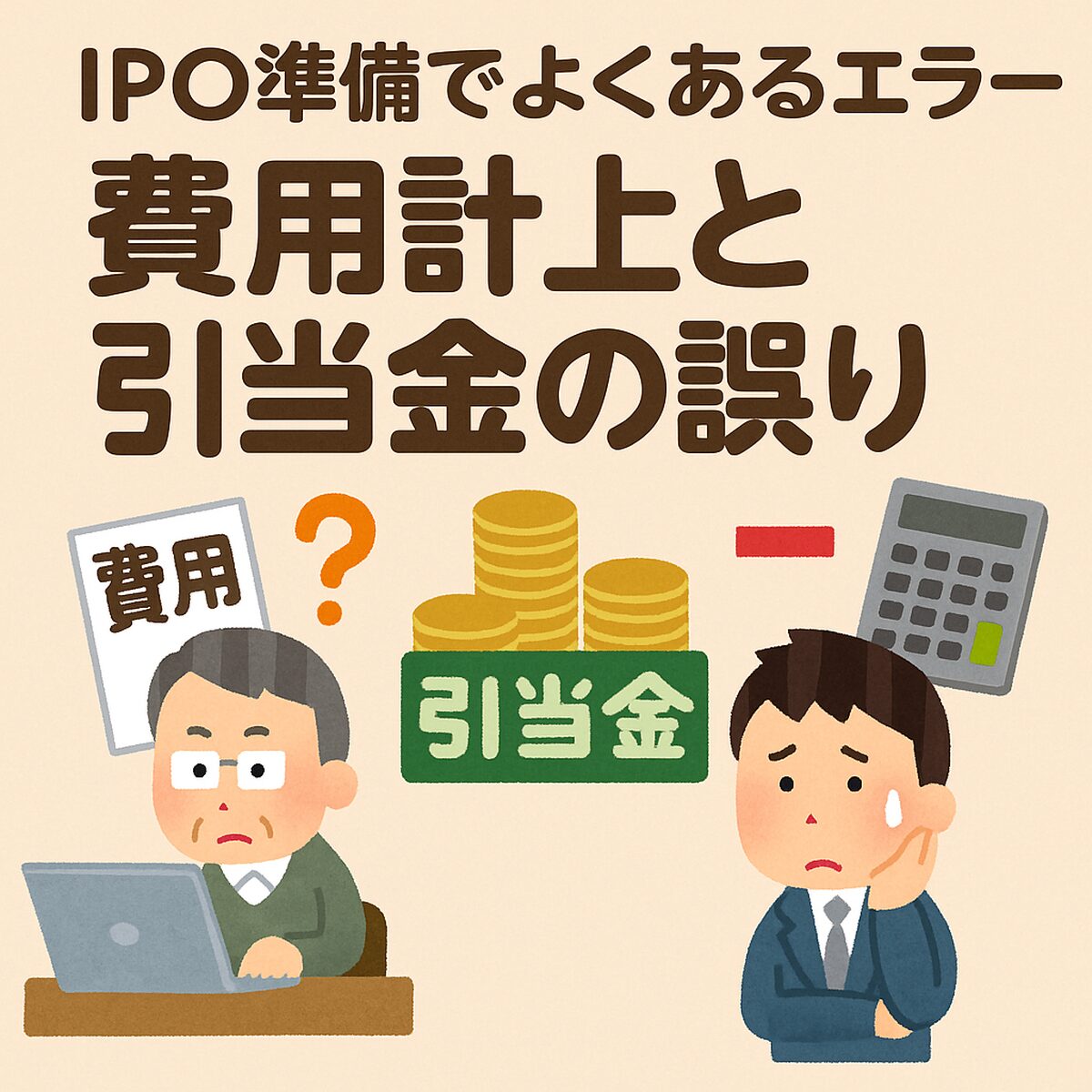IPO監査のトリセツ④|IPO準備でよくあるエラー② 費用計上と引当金の誤り(前半:前払・未払・引当金)
1. なぜ「費用計上の誤り」がIPO監査で問題になるのか
IPO準備において、収益認識以外にも利益インパクトに影響を与える観点から、監査法人が厳しくチェックするのが「費用計上の正確性」です。収益と対応する費用が正しく認識されていなければ、利益が歪み、事業の実態を投資家に誤解させることになります。特にIPO監査では「利益の一貫性」「利益の平準性」が重視されるため、費用の前倒しや後倒しによって利益が大きく変動することは、故意である粉飾であるか故意ではない誤謬であるかにかかわらず重大な指摘を受ける対象となります。
典型的な誤りは以下の通りです。
• 前払費用を一括処理してしまい、実際のサービス提供期間に応じた配分をしていない
• 未払費用を計上せず、期末利益が過大計上される
• 固定資産の減損会計を適用していない
• 引当金を計上せずに実際の事象の発生時点で費用を計上している
いずれも「税務申告では大きな問題とならないが、金融商品取引法に基づく会計では許されない」領域です。監査法人はこうしたズレを発見すると、金額が大きい場合には決算をさかのぼって修正することを要求するため、IPOスケジュールに影響を与えるのです。
なお、税務会計では、税金はなるべく多く早めに取りたいという思考が働くことから費用計上を遅めにし、収益認識を早めにすることについては、税務当局の調査などが入って間違っていても指摘をされることはありません。親切な調査官だと教えてくれることはあるかもしれません。他方、上場会社の会計では、利益の過大計上は投資家に損をもたらす可能性があることから、利益は小さめに保守的に計上することが好まれ、費用計上が遅くなることや収益認識を早めにすることについては、特に敏感となりエラーである場合には、修正が求められる可能性が高くなります。
つまり、税金を申告するための会計と上場会社に求められる会計の好みは真逆なのです。この点から、IPOを目指す前の会社とIPOを目指す会社では、費用計上について大きく修正を要する可能性を秘めているのです。別に、IPOを目指さないのであれば間違いではないのです。
また、税法会計は、課税の公平という理念に基づいて実施される会計であるのに対し、上場会社の会計は、投資家に向けての適正な業績の開示という理念に基づいて実施される会計になります。そのため、上場会社では業績を適切に表示するために期間按分や資産の評価を適切に実施するために、引当金の計上や減損損失の計上などで見積もりの要素の強い処理が増加します。他方、税務会計において、みんなが勝手に都合が良いように見積りを行うと、課税の公平という理念を実現することが難しくなります。そのため、税法ではほとんど見積り処理が認められていません。
なお、減価償却費は一種の見積りになりますが、税法では厳密にルールが決められておりこれを逸脱する処理は認められません。ここで、上場会社の会計では、税法から外れて個々の資産の固有の耐用年数を見積もって減価償却を行うことが合理的なように見えますが、減価償却資産は膨大な数があり、いちいちこれを見積りによりそれぞれの耐用年数を定めることは経済的合理性を害するし、監査法人もイチイチ確認する時間はありません。そのため、減価償却費は税務上の耐用年数を用いれば問題がないという実務慣行が存在します。日本公認会計士協会も監査・保証実務委員会実務指針第81号 「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」という指針を出してこのような実務慣行を許容しています。
2. 前払金、前払費用に関する典型的な誤り
未上場企業で特に多いのが、前払費用を「支払った時点で費用」として処理してしまうケースです。例えば、年間の保険料120万円を1月に一括で支払った場合、本来であれば毎月10万円ずつ12か月に分けて費用計上すべきところ、支払月に全額計上してしまうのです。税法では1年以内の短期の前払費用は支出時に損金計上が認められることから、税理士のみしか関与しておらず税法しか気にしていない会社においてはまずここが引っかかることになります。
この処理を続けると、月次や四半期の利益が大きく変動し、投資家や証券会社から「業績の安定性に欠ける」と見なされます。監査法人からもよほど少額の取引ではない限り、原則として「サービス提供期間に応じて費用を按分せよ」と修正を求められます。
さらに厄介なのは、前払費用の範囲が広いことです。保険料、賃借料、システム利用料、広告費など、さまざまな取引が含まれます。IPO準備の過程では、これらを契約ごとに洗い出し、期間配分を徹底する必要があります。場合によっては、短期前払費用ではなく数年間に及ぶ前払費用があるようなケースでは、過去数年分の支払契約をさかのぼって再計算する必要があり、決算チームにとって大きな負担となります。
3. 未払金、未払費用の計上漏れ
逆に「未払費用」を計上し忘れるケースも典型的です。たとえば、12月に外注作業が完了しているのに、請求書が翌年1月に届いたため、当期の費用に計上しない、といった事例です。また、賞与や未払の残業代を期末に未払計上せず、支払時にだけ費用化するケースもよく見られます。
この場合、当期の利益が実態より大きくなり、適正な期間損益計算ができていない状況にあります。監査法人は、支払伝票や契約書、稟議書などを丹念に精査し、計上漏れがないかを確認するように依頼が来ますし、監査法人自らもカットオフ手続として証憑レベルまで調査を実施します。もし未払費用の漏れが多発していれば、「決算統制が機能していない」と判断され、内部統制が適切に機能していないのではないかなどと深刻な疑念を招くことになります。特に、決算月は経理から全社に宛ててメールなどで、証憑の提出漏れがないように注意喚起を実施するなどの対応が必要となります。また、定型的なコストについては管理簿などを作成しておけば、経理への未達の証憑について、経理部側からの問合せを実施することがかのうになりますし、毎月定額に近いケースでは見積り計上を行うことも可能になります。
未払費用は、「請求書が来ていないから計上しない」という安易な判断が最も危険です。IPO水準では、実際の役務提供や作業完了の事実に基づいて計上判断を行うことが求められます。
ちなみに、監査法人はアンレコチェックという名前の手続で、費用計上のカットオフエラーの検証手続をほぼ必ず実施します。この手続で特にテレビでのコマーシャル放映などでとても大きな金額のエラーが見つかって一大事になった経験が2回くらいあります。払ったのは決算期後だけれども、放映は決算期内というケースで何億円もの費用計上漏れみたいなことがありました。
4. 固定資産の減損会計の不適用
固定資産は将来この固定資産の利用から利益を出すことができない状況にある場合には、将来のマイナス分について固定資産の簿価を減額して費用処理することが求められます。固定資産の減損損失は税法上では損金として認められないことから、税法会計で経理を行っていない場合には、申告書上でいたずらに調整する必要性が生じることから固定資産の減損会計を適用していないのが一般的です。そもそも、必要がないので当然です。
ただし、IPOを行って、上場する場合には、投資家に対して適切に会社の業績を見せる必要があることから固定資産の減損会計の適用は必須となります。
IPO審査では「適正な業績を表示するために適切な会計方針を採用しているか」が重視されるため、固定資産の減損会計の適用は必須となります。
5. 費用計上エラーがIPOスケジュールに与える影響
前払・未払費用、前渡金は、一見些細な処理に見えますが、IPOスケジュールに重大な影響を与えます。監査法人が過去数年分の取引を精査し、修正仕訳を大量に求めると、それだけで決算スケジュールが遅延する可能性があります。特によくある事例として、海外の仕入先に前渡しをしているケースで、外貨換算が適切にできていないことにより過去から累積された前渡金の不明残高が多額に発生しており過去数年に遡って原因を検証する必要が生じた場合などで大きな苦労をすることになります。
特にここが間違うとそもそも最低限のレベルに達していないとの判断に、監査法人のチェックは厳しく、投資家の信頼も直結します。費用計上の誤りを放置したままIPOを進めることは、ほぼ不可能と言えるでしょう。
6. 賞与引当金の未計上
賞与を毎年支給しているにもかかわらず、期末に引当金を計上していないケースは非常に多いです。 「賞与は支給決定時に計上する」という税務的な考え方のまま放置され、結果として「本来計上すべき費用が翌期に繰り延べられている」状態になります。
IPO監査では「当期の労働対価を正しく費用化していない」と指摘され、見積もりを行ったうえで修正をする必要があります。特にストックオプションなど株式報酬を導入している企業では、場合によっては、賞与引当金と併せて人件費全体の正確な見積りが必須です。
7. 退職給付引当金の放置
退職給付引当金は、未上場企業で最も計上漏れが多い科目の一つです。 「従業員の退職金は退職時に計上すればよい」と誤解されがちですが、会計基準では「将来の退職給付を見積もり、当期の労働対価として費用化」する必要があります。
IPO準備段階で初めて退職給付債務を算定した結果、数億円規模の負債が一気に表面化し、財務体質が大きく変わるケースも珍しくありません。
8. 「粉飾疑念」と誤解されやすいリスク
費用計上や引当金の誤りは、意図的な粉飾ではなく単なる「税務処理の延長」であるケースが大半です。 しかし投資家から見れば「利益かさ上げ」と区別がつきません。
• 前払費用を一括計上 → 利益が年度ごとに凸凹
• 未払費用の漏れ → 利益が実態よりも高くなる
• 引当金未計上 → 将来の費用を先送りし、見かけ上の利益を水増し
こうした誤りは「ガバナンスの欠如」と直結して評価されるため、IPO審査前に修正をして、エラーを生じない体制を構築しておく必要があります。
9. 実務対応(規程化・早期決算・システム化)
費用計上エラーを防ぐには、以下の3点が必須です。
1. 規程化
前払費用・未払費用・引当金の処理ルールを明文化し、社内規程として浸透させる。
2. 早期決算スケジュール
期末直前に全取引・契約をチェックし、未払・前払を漏れなく確認する体制を作る。
3. システム化による自動按分
Excelでの管理には限界があるため、会計システムやERPに「月割機能」「引当金自動計算機能」を導入するなどの対応が必要となるケースもありえます。
IPO準備企業の多くは、監査法人から「人力依存の決算はIPO水準に達していない」と指摘されることも多く、システム化を要請されるケースもあります。
10. チェックリスト:費用計上・引当金で詰まらないために
• 前払費用をサービス提供期間に応じて配分しているか
• 期末の未払費用を網羅的に把握できているか
• 固定資産の減損会計が適用されているか
• 賞与引当金を毎期見積計上しているか
• 退職給付引当金を算定・計上しているか
• 決算スケジュールの中で営業・人事部門と情報連携しているか
• システム化により人的ミスを最小化しているか
11. まとめ
費用計上と引当金の誤りは、IPO準備において収益認識に次ぐ大きなリスクです。 特に引当金は、誤解されると「粉飾疑念」に直結し、投資家からの信頼を大きく損ないます。
IPOを成功させる企業は、例外なく「費用計上ルールを明文化し、決算早期化とシステム化で安定運用している」点で共通しています。監査法人が「安心して監査できる会社」と評価すれば、スケジュール・コストともに大きな改善が見込めます。