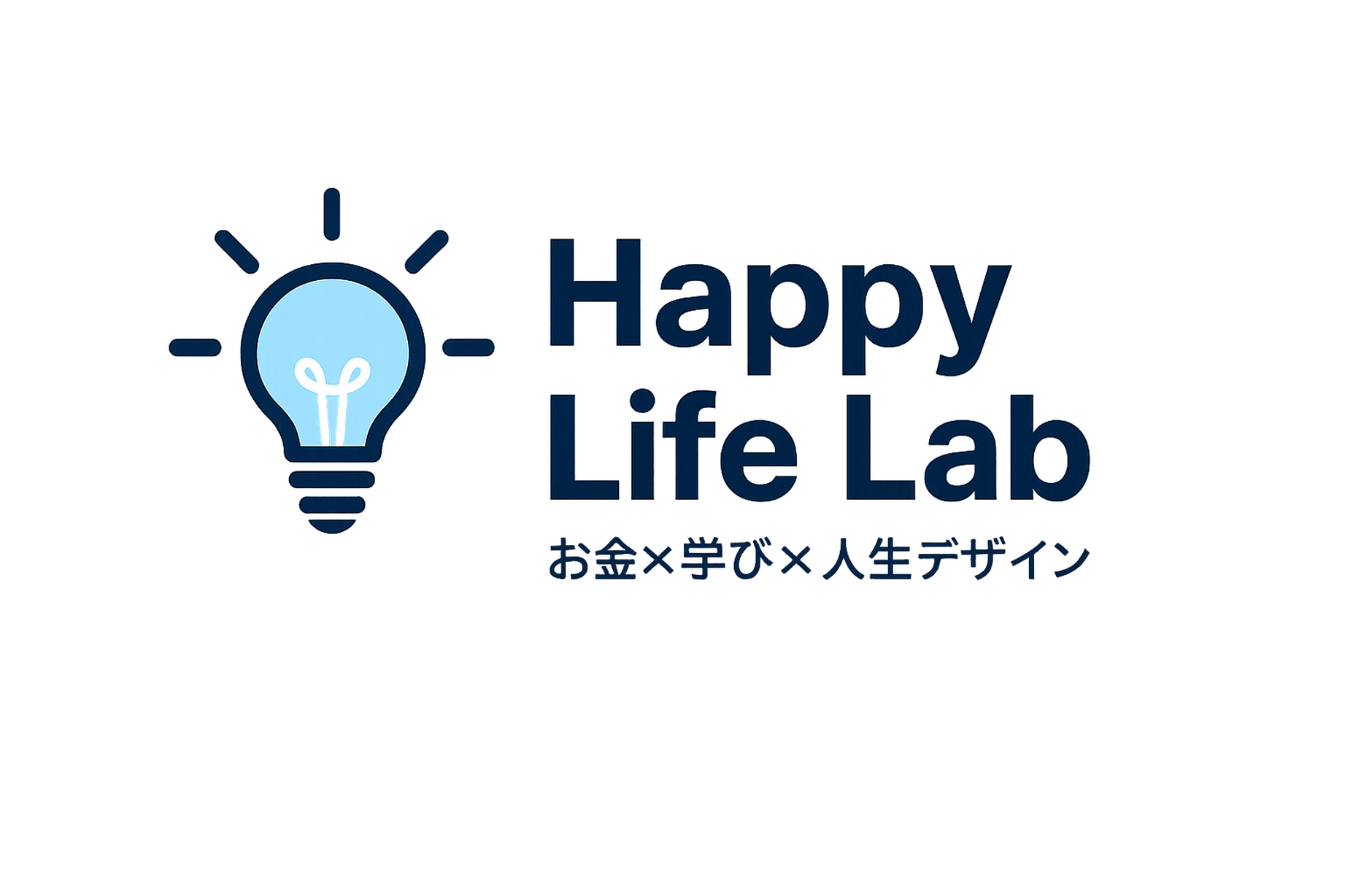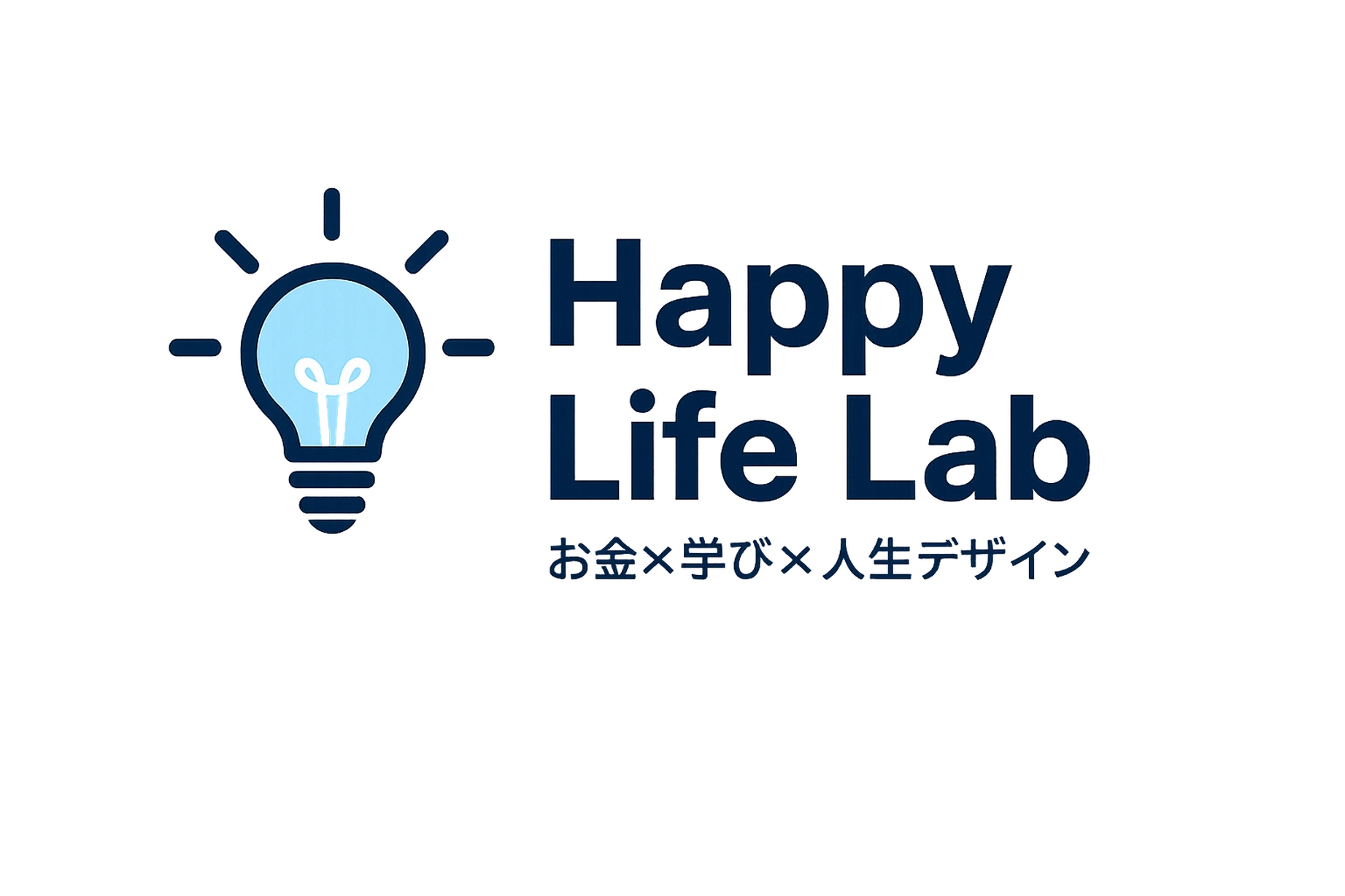IPO監査のトリセツ④|IPO準備でよくあるエラー③ 在庫評価と棚卸資産の不備
1. 在庫はIPO審査で頻繁に問題になる
IPO準備企業にとって「在庫(棚卸資産)」は、ほぼ必ず監査法人に指摘される領域です。理由は単純で、在庫は貸借対照表で大きな割合を占めるだけでなく、売上原価や利益に直結するからです。
IPO準備で典型的に問題となるのは以下の3点です。
• 在庫の実在性:帳簿上の在庫と実地棚卸が一致していない
• 在庫の評価方法:税務処理と会計基準のズレ
• 在庫の評価減:滞留・陳腐化在庫を放置している
在庫の評価を誤れば、利益が大きく歪み、投資家を誤解させるリスクが極めて高いです。また、在庫の増減によって利益操作は容易にできます。在庫はそもそも比較的変動があって当たり前のものであり、かつ原価計算を経由する場合には算定方法が複雑なケースもあり、隠蔽を比較的行いやすいことから意図的に利益操作をする粉飾に利用されがちな科目になります。
これらの観点から、在庫は非常に重要な科目になるのです。
2. 在庫の「実在性」に関する誤り
最も多いのが「帳簿と現物が一致していない」ケースです。特に製造業や卸売業では、以下のようなエラーが頻発します。
• 実際には出荷済みなのに帳簿に残っている(ダブり計上)
• 廃棄した在庫が帳簿に残っている(不良在庫の放置)
• 実際には倉庫に存在しないのに帳簿上は存在している(架空在庫)
製造業や卸売業のような業種においては、監査法人は年に最低1回は棚卸立会という会社の棚卸に監査人自らが立ち会う手続を実施します。「帳簿と現物が一致していない」ケースは、監査法人が棚卸立会を行うことにより、簡単に発見される性質のエラーであることから修正を迫られることになります。なお、会社が自ら棚卸でこのようなエラーを検出できない場合には、会社の棚卸は実質的に機能しておらず内部統制が有効に機能していないと判断されてしまうことになります。
IPO準備の段階では、このような会社の棚卸が実質的に機能するように棚卸の仕組みを適切に構築したり、「帳簿と現物が一致していない」ケースそもそもなくすような在庫管理の仕組みを構築する必要があります。在庫管理は、会社の本業に関する部分であるため、この部分の管理体制が適切に構築できない場合にはいたずらにIPOのスケジュールが遅延するということになりますし、これができないなら一旦出直してきてくださいと言いたくなるような状況になります。
3. 在庫差異が出やすい典型パターン
監査法人が特に問題視するのは「棚卸差異の多発」です。典型的なパターンは次の通りです。
• 倉庫ごとに在庫管理方法が異なり、集計が合わない
• 同一種類の在庫が複数のロケーションに存在することにより数量の管理が適切にできていない
• Excel管理で人的ミスが頻発している
• 外部倉庫や委託先の在庫を把握していない
• 棚卸を毎期きちんと行わず、帳簿在庫が実態から乖離しており常に不明差異が存在する
なお、発生した棚卸差異については、必ず差異調整を実施することを求められますが、ここで会社が原因の把握ができないとさらに大きな問題となります。そのため、差異要因を適切に把握する体制を構築することも大事になります。
4. 在庫払出方法の誤り(税務処理とのズレ)
未上場企業でよく見られるのが、税務処理をそのまま会計処理に流用しているケースです。「最終仕入原価法」は、税務では認められても、上場会社に求められる会計基準では重要性のない在庫についてのみ許容されており、一般的な商品、製品、仕掛品、原材料については、「先入先出法」「総平均法」「移動平均法」などのより精緻な在庫の払い出し方法の利用が求められます。
具体的には:
• 税務では認められる在庫払出しの「最終仕入原価法」を、会計でもそのまま適用している
• 原価計算の基礎データが不十分で、平均単価が正しく算出されていない
この部分で、税務と会計でズレが出ると大変なので、税務と会計を一致させて「先入先出法」「総平均法」「移動平均法」などの方法を採用すると良いと思います。なお、ときどき、「総平均法」は簡便なのでダメと主張をしてくる会計士がいますが、「総平均法」は会計においても許容されている在庫の払い出し方法であるため、この主張は誤りであると個人的には思っています。もちろん、実態に合わせて払い出し方法をチョイスする必要があるのですが、「先入先出法」「移動平均法」などと完全に一致して厳密に「先入先出法」「移動平均法」で実際に払い出しを行っているケースは少ないと思われるからです。厳密に一致する払い出し方法がないという状況であるならば、一致はしない中でより簡便な方法を採用するというのは理論的にも排除される性質の話ではないと思っています。
5. 在庫評価減(陳腐化・滞留在庫)の放置
IPO準備企業が見落としやすいのが「在庫の評価」の問題です。会計基準では「在庫に収益性の低下が生じている場合は評価減を行う」と定められています。具体的には、在庫の価値が取得価格(帳簿価額)を下回る状態を指します。このような状態は、陳腐化、劣化、市場価値の低下などによって起こります。これは、「正味売却価額(将来の販売で得られる価格)」「再調達原価(市場でそれを再調達するために必要な価格)」が「帳簿価額」を下回ると判断されるような状態であり、在庫の帳簿価額を正味売却価額や再調達原価まで切り下げる会計処理が必要となります。
しかし、未上場段階では「不良在庫があっても、税務上損金算入できるときに処理すればよい」と考え、評価減を怠るケースが多いのです。というよりは、未上場段階では、適正な期間損益計算が求められておらず、なるべく簡便に税務申告を行うという観点しか考える必要がないため、簡単に税務申告を行う観点からは在庫の評価を行うべきではないのです。
• 数年以上動いていない滞留在庫を帳簿価額のまま放置
• 技術革新で陳腐化した製品を評価減せずに計上
• 販売見込みのない試作品を資産として残している
6. 在庫に関する「粉飾疑念」
在庫評価の誤りは、投資家から「粉飾の温床」と疑われやすい領域です。架空在庫や評価減の放置は、過去の粉飾事件でも繰り返し問題となってきました。
IPO監査や審査では「利益をかさ上げするために在庫を過大計上していないか」などもチェックポイントとなります。仮に意図的に行っていない場合であっても、在庫差異や評価減漏れが多発すれば、会社の内部統制に欠陥があるとみなされて、上場延期や信頼失墜にもつながる可能性すらあります。
7. IPO直前に発覚する「在庫NG事例」
IPO準備の現場で、大きなインパクトを持つのが「在庫評価に関する不備が直前で発覚する」ケースです。このような場合には、以下のようなケースですら想定されます。
• 在庫差異が数億円規模で発覚:棚卸の精度が低く、IPO審査直前の在庫調査で大規模な差異が見つかり、監査法人から「内部統制不備」と判定され延期。
• 評価減を怠り一括損失計上:滞留在庫をIPO直前に評価減、利益急減で証券会社が上場を延期。
• 委託倉庫の管理不備:外部倉庫の在庫証憑を示せず、監査法人が承認せず上場を延期。
私は、IPOの準備会社の監査で、棚卸のやり直しを経験したことがあります。それくらい、棚卸による実際在庫数量の確定は重要な手続になるのです。
8. 投資家視点から見た在庫リスク
投資家は、在庫を単なる資産ではなく「リスクの塊」と見ています。
1. 流動性が低い(現金化に時間がかかる)
2. 陳腐化・劣化で評価減リスクが常に存在
3. 売上に比べて過大な在庫は「需要減少疑念」につながる
特にIPOでは「在庫回転率」「棚卸資産回転期間」が注目されます。これが同業比で悪ければ、投資家は事業モデルそのものに懸念を抱きます。
9. 在庫評価に関する監査法人の注目ポイント
監査法人はIPO監査で以下を徹底的に確認します。
• 実在性:現物確認・棚卸立会
• 網羅性:子会社・委託倉庫含め全在庫を計上
• 評価妥当性:正味売却価額などを踏まえた評価減の有無
• 評価妥当性:「腐食」や「腐敗」のない在庫の陳腐化、過剰在庫などの評価基準の有無
さらに内部統制整備(棚卸手順・承認フロー・システム統制)も重要視されます。
10. 在庫管理でよくある失敗パターン
IPO準備企業で頻発する在庫管理の失敗は以下の通りです。
• 年1回しか棚卸をせず、長期間実棚がないことに起因して差異調整が困難となるケースが頻発
• 倉庫ごとに管理ルールが異なり集計不能
• サンプル品・展示品を在庫に含めず過少計上
• Excel管理が不十分で人的ミス多発、統制証跡も残らない
• システム管理で当日しか数量が残らず、後日当日の数量の証跡が残っていない
11. 実務対応(定期棚卸・システム管理・評価減の早期化)
在庫リスクを抑えるための実務対応は以下の通りです。
1. 定期棚卸を年1回でなく半期ごとに実施、差異を早期把握し、差異が発生しないように管理。
2. Excelで管理できない大量の在庫がある場合にERPや在庫管理システムを導入、在庫を一元管理。
3. 滞留・陳腐化は適切に評価減を計上する仕組みを構築。
4. 委託倉庫は定期確認や第三者証憑で裏付けをできるように管理体制を構築。
12. チェックリスト:在庫評価で詰まらないために
• 帳簿と実地棚卸が一致しているか
• 滞留・陳腐化在庫をリスト化し評価しているか
• 倉庫ごとに在庫管理ルールを統一しているか
• 委託倉庫・外部在庫を網羅的に把握しているか
• 棚卸手順をマニュアル化し内部統制を整備しているか
• 在庫回転率を同業他社と比較し投資家懸念を払拭できるか
13. まとめ
在庫評価と棚卸資産はIPO準備における「大きな関門」です。収益認識や費用計上が整っていても、在庫の計上状況が不透明な場合には投資家は納得しません。
成功企業は以下を徹底しています。
• 棚卸とシステム化で実在性・網羅性を確保
• 滞留・陳腐化を評価し透明性を担保
• 在庫に関する内部統制整備・運用で監査法人から「監査しやすい会社」と評価される
反対に、在庫を放置した企業は、IPO直前に修正を余儀なくされ延期・中止に直結します。
在庫は「資産」であると同時に「リスク」。IPO準備段階から徹底整備することが投資家信頼を勝ち取る方法です。