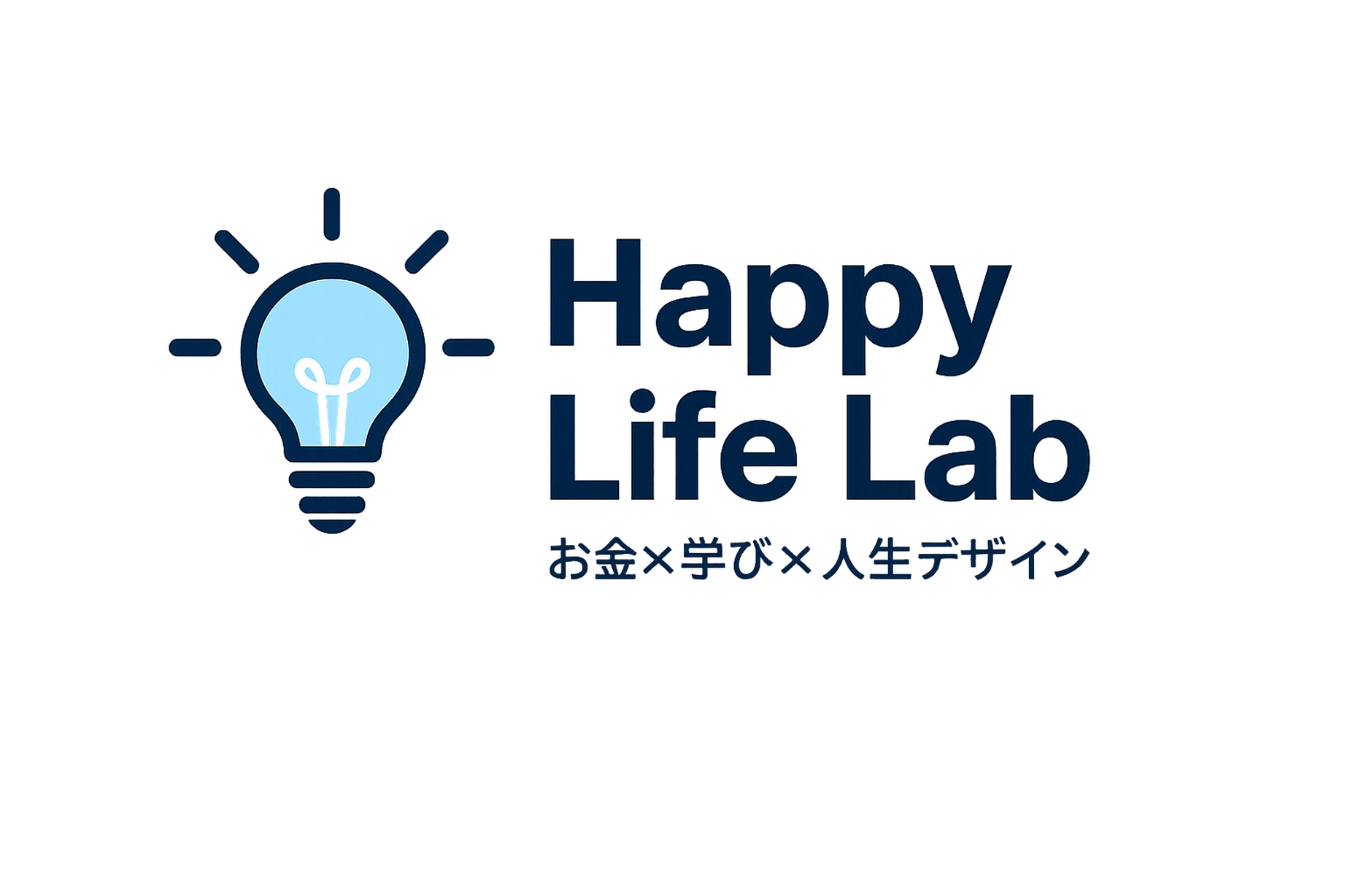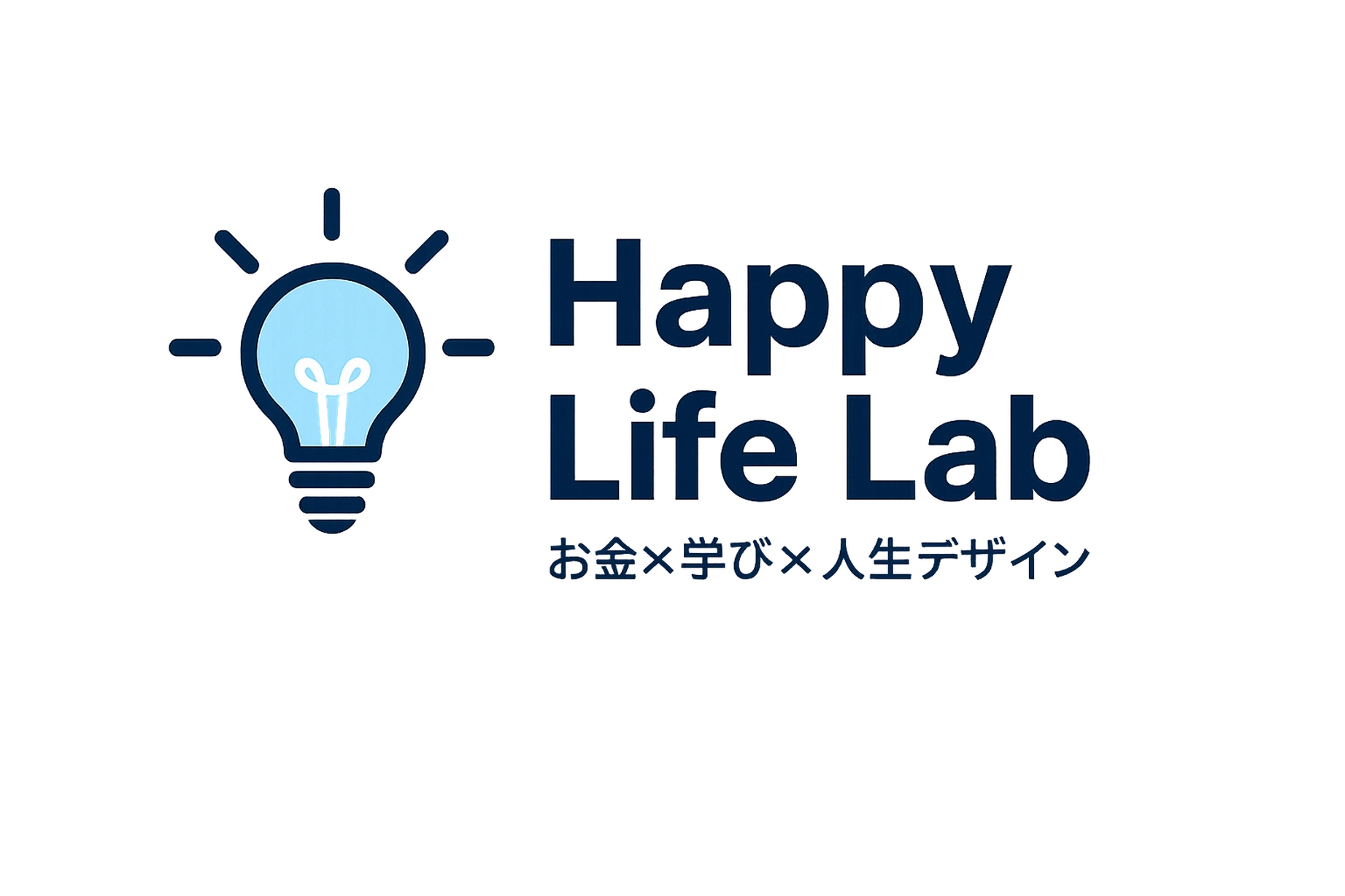3月決算の裏側と監査法人の繁忙期|会計士が語る「4〜5月地獄」
こんにちは、公認会計士のHappy Master JOYです!
今回は「監査のトリセツ」第2回。テーマは「3月決算の裏側と監査法人の繁忙期」です。
日本企業の多くが3月決算を採用しているため、公認会計士にとって4〜5月は“修羅場”のような時期。
「ゴールデンウイーク?なにそれ美味しいの?」という状態に陥る会計士も少なくありません。
この記事では、なぜ3月決算が集中しているのか、監査法人の繁忙期の実態、そして非常勤制度や人材不足の課題まで、現場のリアルを会計士目線で語ります。
なぜ日本企業は3月決算が多いのか
日本では圧倒的に3月決算の企業が多いのはご存じでしょうか。
理由は単純で、国や自治体の会計年度(4月〜3月)と揃っているため、税務や行政との整合性が取りやすいのです。学校とかも年度は4月~3月となっていますよね。
また、多くの親会社が3月決算を採用しているため、グループ子会社も合わせざるを得ない構造になっています。結果として、監査法人の業務も3月決算企業の監査に一気に集中。
つまり、国全体が一斉に決算→監査→申告を行う「年度末ラッシュ」構造になっているわけです。
会計士たちの「4〜5月地獄」
3月決算の監査は4月初旬から本格化し、ピークは4月中旬〜5月中旬。
この1か月ほどはまさに「監査法人の戦場」です。
朝から晩まで現場に詰め、土日返上、ゴールデンウイークは“幻”。
繁忙期の監査法人では、事務所の照明が深夜まで消えません。
新人もベテランも関係なく、調書作成・レビュー・問い合わせ対応に追われます。
実際に私も大手監査法人時代は、午前4時にオフィスを出て午前10時に再出社、なんて生活をしていました。
会計士受験時代の勉強もハードでしたが、実務に出てからのこの時期こそ「ほんとうの修行」と言えるかもしれません(笑)。
以前に比べて、大手の監査法人は労働基準監督署が厳しい影響もあり、監査の若手スタッフがこのように深夜残業することはなくなっていると聞いていますので、この記事をご覧になった受験生の皆さんはご安心ください。最近は、新人が午前様ということはないように聞いています。
ゴールデンウイークは「存在しない祝日」
監査法人の内部では、繁忙期対応のために祝日を平日扱いにして、別の時期に代休を取るという「変則カレンダー」を採用しているところもあります。
ただ、6月や8月の閑散期に少し休みを取れるとしても、正直「燃え尽き症候群」状態。
精神的にも体力的にも、かなりの消耗戦です。私は、大手監査法人時代は、IPO部門にいたのでゲリラ戦専門のゲリラ部隊のようなポジションにいたので、日々生きるか死ぬかのような状態でした。年中繁忙期という感じでしたが、普通は繁忙期以外はまぁまぁ普通の生活ができるようです。
こうした過激な繁忙期を乗り越えることでチームの結束が生まれ???、会計士としての地力もついていきます。
地味ですが、この時期こそが会計士をプロフェッショナルへと鍛える“試練の季節”なのです。
と、綺麗ごとも書きましたが、若手の時期だけでは終わらずに、いつまでも忙しい世代もいるのが現実なようです。2010年前後に合格した会計士などで、現在、大手監査法人のマネージャーくらいになっている場合は、若手を酷使できないことから若手時代は自分がいちばん忙しく、マネージャーになっても自分が忙しいみたいな話を聞いたことがあります(笑)
監査法人のリソース問題と非常勤制度
ここ数年、どの監査法人も慢性的な人手不足に悩まされています。
景気が良くなれば監査依頼が増え、人が足りない。景気が悪くなればクライアント数が減り、人が余る。
こうした循環を、合格者数の増減だけで調整するのは現実的ではありません。
そのため、私は個人的に「非常勤会計士の積極的活用」が重要だと考えています。
ベテランの非常勤会計士が増えれば、繁忙期の監査品質を落とさずにリソースを確保できる。
新人を大量に採用して一時的に数を埋めるよりも、結果的に品質面では安定します。
ただし、金融庁は「非常勤だと品質が下がる」として常勤化を推奨する傾向にあるようです。
しかし、現場で感じる実態はむしろ逆。
経験豊富な非常勤会計士は、責任感を持って自律的に仕事を進める人が多く、レビューの効率も高いです。
数合わせよりも「質の確保」に軸を置いた体制づくりが、今後の監査法人には求められるでしょう。育てられないのに中途半端に中小監査法人で新人を取るのは非常に良くないのではないかとの認識でいます。やはり、監査を継続するにせよ、事業会社に行くにせよ、独立するにせよ大手の監査法人で3年~5年は経験したうえ自分の目指す方向に行くと、その後優秀な会計士として成功できるようなイメージでいます。大手の監査法人での経験を有する会計士は非常勤としても優秀な方が多い気がします。もちろん個人差はあります(笑)
3月決算集中の弊害と“ずらす”戦略
会計士のリソース不足が毎年繰り返される根本原因は、3月決算に集中しすぎていることです。
実は、決算期を変更することで監査報酬を抑えられるケースがあります。
たとえば6月決算や9月決算の会社は、監査法人の閑散期に当たるため、比較的リーズナブルな報酬設定になる傾向があります。
税務面でも、3月決算を避けることでメリットがある場合があります。
たとえば税務調査の多くは夏以降に集中するため、決算期がその時期から外れている企業は調査対象になりにくいとも言われています(国税OB談)。
最近では、上場を目指すスタートアップ企業の中にも、あえて3月決算を避けて「8月決算」や「10月決算」などの3の倍数月以外を採用する動きが広がっています。
この“ずらす戦略”は、結果的に監査の安定化にもつながる合理的な選択です。監査を受けるクライアント側としても報酬が多少安く受けてもらえる可能性もあります。
繁忙期を支える「チーム力」と「現場の知恵」
繁忙期を乗り越える最大のカギは、チーム力と現場の知恵です。
監査という仕事は、個人プレーでは成り立ちません。
現場では「誰がどの科目を担当するか」「どのレビューをいつ通すか」「差異調整を誰がまとめるか」など、細かな役割分担とスケジューリングが命です。途中で予期せぬトラブルが発生しない限りは、現場に入る前の下準備ですべて監査は終わっていると言っても良いのかもしれません。もちろん途中で予期せぬトラブルを発生させないためにも、事前の準備が大事です。
とくに4月の後半は、全員が疲労のピーク。
そこで大切なのが“お互いさま”の精神。
自分の担当が終わったら他メンバーをフォローする、ミスを責めずにリカバリーを優先する——こうしたチーム文化が根付いた監査法人ほど、繁忙期をうまく乗り切れます。意外と皆さん自分が終わったら終わりなんですけどね。辛口ですね(笑)。
非常勤の新しい価値と働き方の多様化
非常勤会計士は「子育て中」「副業」「地方在住」など、働き方の多様性を支える存在でもあります。
AIやリモートワークの普及によって、監査の一部作業はオンライン化が進んでおり、
今後は「常勤か非常勤か」という区別自体が薄れていく可能性もあります。
たとえば、クラウド上での調書共有、Zoomを使ったクライアント対応、電子確認状の導入など、
監査の現場も確実にデジタル化が進んでいます。
こうした仕組みをうまく活かせば、「繁忙期=出社地獄」という構図も少しずつ変わっていくかもしれません。
特に個人的には、AIに試算表や仕訳を読み込ませて、増減分析を行うことができるようになれば会社に聞く頻度も減るし、監査の効率化に繋がっていくように思います。仕訳テストなどは特に今後はAIが活躍する舞台になるのかもしれません。
まとめ:繁忙期の裏側にある“誇り”
3月決算の監査は確かに大変です。
でも、全国の上場企業の決算書が社会に公表されるのは、この時期に多くの会計士が懸命に働いているおかげでもあります。
投資家や金融機関が安心して企業情報を利用できるのは、監査という「見えない努力」の結果なんです。
もし今、監査法人で働いていて「もう限界かも…」と思っている方がいたら、少しだけ立ち止まってみてください。
あなたの作る1枚の調書が、企業の信頼を支えている。
それって、すごく誇れることです。たぶん。。。。。きっと、、、そうかもしれない。
あっそ、って言いたくなるかもしれませんけどねー💦
次回は「監査チームの分担と科目別の難易度」をテーマに、現場でのリアルな仕事の流れを紹介します。
お楽しみに!