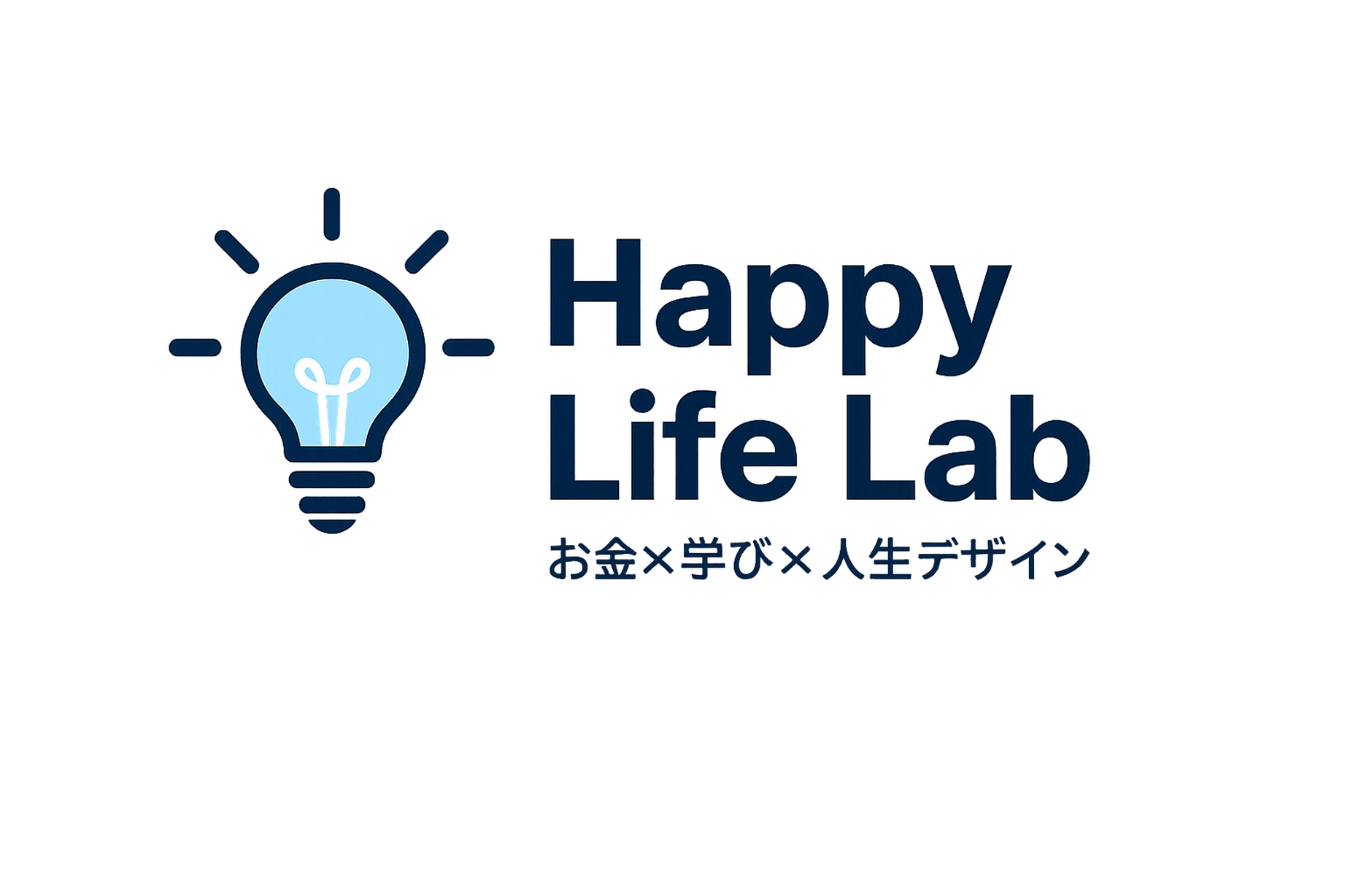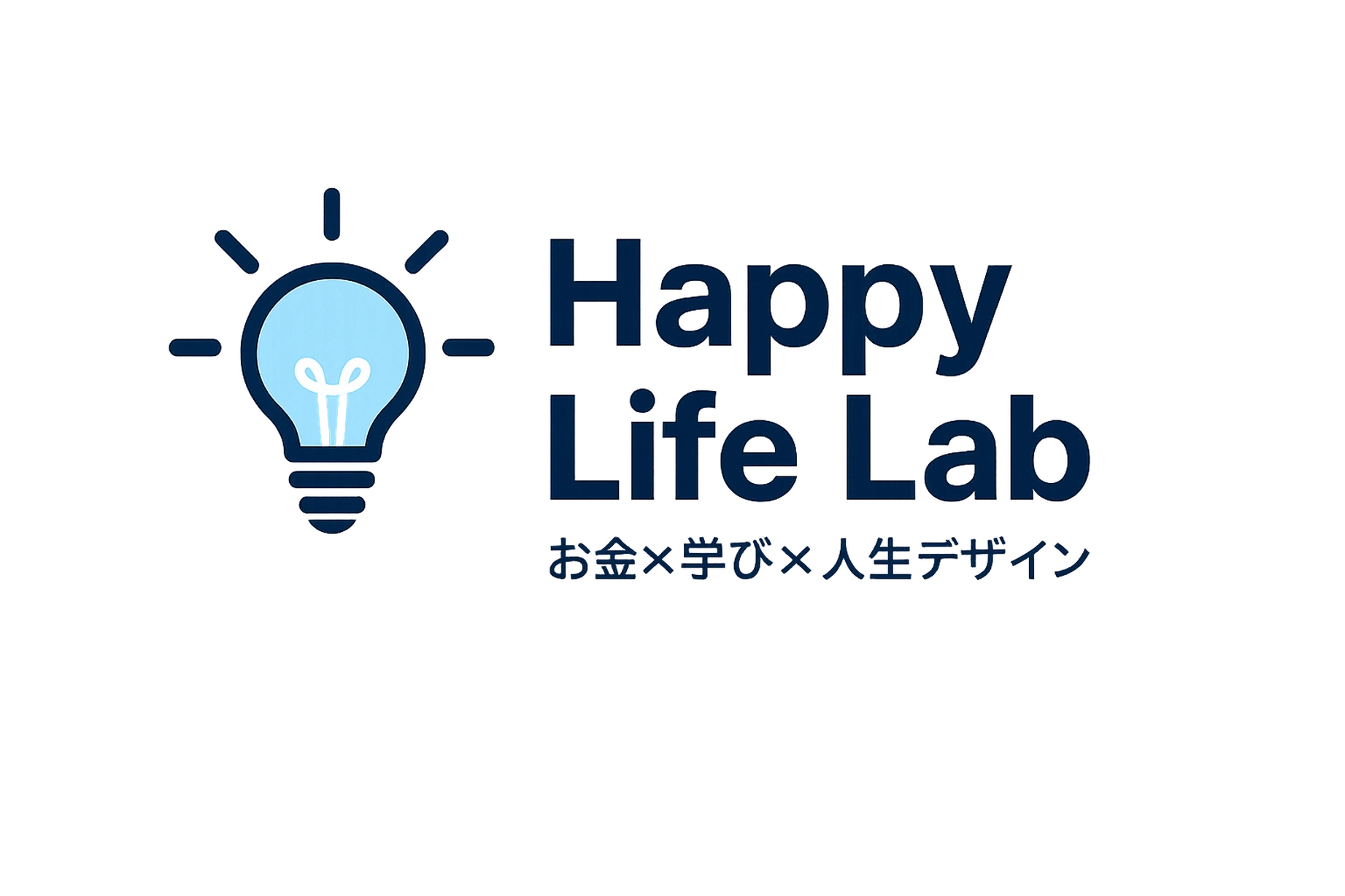行動ファイナンスとは何か(前編)|投資判断を狂わせる心理の罠を読み解く
こんにちは、JOYです!
「投資のトリセツ」シリーズ第2回は、行動ファイナンスについて取り上げます。
投資で失敗する多くの原因は「知識不足」ではなく「心理の罠」に引っかかることにあります。
この分野を理解することで、あなたの投資が安定、向上することが期待できます。少なくとも大きな失敗をする可能性を減らすことができるでしょう。
1. 行動ファイナンスとは何か
行動ファイナンス(Behavioral Finance)とは、人間の心理や行動の偏りが、投資や経済行動にどのような影響を与えるかを分析する学問です。投資というのは人間の心理的な側面の影響をものすごく受けるものであるので、私も過去にはメンタルがもの凄く揺さぶられた経験があります。簡単に言うと、眠れなくなります(笑)
伝統的な投資理論、金融理論では「人は合理的に行動する」とされてきましたが、現実の市場ではそうはなりません。
人は恐怖や欲望、期待、焦りなどの感情に左右され、結果として合理性から逸脱した判断を下します。投資には心理学的な側面から研究を要する必要があり、投資研究に心理学を組み合わせたものが行動ファイナンスなのです。
たとえば、株価が上昇しているときには「もっと上がる」と感じ、下落しているときには「まだ下がる」と思ってしまう。
その背後にあるのが、行動ファイナンスで説明される数々の心理バイアスなのです。
2. 投資家が陥りやすい代表的な心理バイアス
ここでは、実際の投資行動で頻発する心理的な傾向(バイアス)を紹介します。バイアスとは先入観や偏見といったものであり、これらを理解することが、投資を心理的な側面から理解するまず第一歩です。
① 代表性バイアス
人は「最近の出来事」を過大に評価し、長期的な平均や確率を軽視する傾向があります。
「最近上がっている銘柄だからまだ上がる」「去年儲かった手法だから今年も通用する」──こうした思考は、代表性バイアスに支配されています。
メガネをかけた真面目そうな人は、スポーツ選手より文系の人に見えますよねー!ですが、メガネをかけた真面目そうなスポーツ選手もいますよね。
② 確証バイアス
自分の信念を裏付ける情報ばかりを集めてしまう現象です。
「この企業は有望だ」と思った瞬間、ポジティブなニュースだけを探し、ネガティブな情報を無意識に避けてしまいます。
人間は、自分にとって都合が良い情報だけ集めがちですよねー。。。
③ アンカリング効果
最初に見た価格や数値に引きずられる心理です。
たとえば「以前1万円だった株が8,000円だから割安だ」と考えるのは典型的なアンカリング。
実際の価値や業績ではなく、過去の数字に囚われることで判断を誤ります。
④ 損失回避バイアス
人は同じ金額の利益よりも損失を強く恐れる傾向があります。
10万円の損失の痛みは、10万円の利益の喜びの約2倍といわれています。
この心理が「損切りできない」「含み損を放置する」といった行動につながります。
プロスペクト理論ですよね。1円でも損はしたくないから来ての、1円でも利益は確定したい。1円でも損したくないから1円でも利益確定するという心理からの行動で、1円の損は、1円の利益よりも心をザワつかせるところから来てます。
⑤ 過信バイアス
自分の判断力を過信する心理です。
短期的に成功体験を重ねると、「自分は市場を読める」と錯覚し、リスクを過小評価する傾向があります。
この状態でポジションを拡大すると、想定外の下落局面で致命的な損失を負うこともあります。
右肩上がりの相場で、たまたま売り買いをして継続的に儲かったけど、その後にレンジ相場や下落相場になって、単に右肩上がりで勝っていただけーというのは典型的な過信バイアスですよね。
3. 心理が市場を動かすメカニズム
市場全体も、人間の集合体に過ぎません。
投資家が共通して同じ心理状態に陥ると、価格は合理性を失い、「過熱」や「暴落」を引き起こします。
たとえば、株価が急上昇する局面では「乗り遅れたくない」という感情が広がり、さらに買いが集まる。
逆に暴落局面では「もうダメだ」という恐怖が広がり、売りが売りを呼ぶ。
つまり、**市場の波は投資家の感情の波**なのです。
株価が継続して上昇している局面では、投資を始める人が多いですよね。逆に株価が継続して下落している局面で投資を始める人は少ないし、相場にいる人も少なくなります。
4. 会計士として見た“心理が生む数字の歪み”
私が監査業務に携わっていた頃、上場企業の経営者や投資家と接する機会が多くありました。
その中で痛感したのは、「数字は冷静に見えて、実は心理の産物である」ということ。
たとえば、同じ業績数値を見ても、人によって解釈が全く違うのです。
強気の経営者は「順調だ」と言い、慎重な投資家は「リスクが高まっている」と感じる。
この“人の見方の違い”こそが市場を動かします。
行動ファイナンスを学ぶ最大の意義は、他人の心理を読むことではなく、**自分の心理を知ること**にあります。
そして、それを認識できた人から、投資で安定した成果を出せるようになります。
後編では、ノーベル経済学賞を受賞した「プロスペクト理論」や「群集心理」の具体例を交えながら、投資家がどう感情に打ち勝つかを掘り下げます。
行動ファイナンス(後編)|プロスペクト理論と群集心理、感情を制する投資術
前編では、投資判断を狂わせる心理的バイアスの仕組みを紹介しました。
後編では、行動ファイナンスの中核理論である「プロスペクト理論」や「群集心理(Herd Behavior)」を中心に、感情を制するための実践的アプローチをお伝えします。
1. プロスペクト理論:損失の痛みは利益の2倍
プロスペクト理論(Prospect Theory)は、ノーベル賞学者である心理学者ダニエル・カールマンとエイモス・トベルスキーが提唱した理論で、人の意思決定がいかに「非合理的」かを示した画期的な研究です。
この理論の核心は、「損失の痛みは利益の喜びの約2倍強く感じる」という点です。
たとえば10万円の儲けよりも、10万円の損失の方が心理的に深く刺さります。
そのため、投資家は利益を早く確定しようとし、損失は「取り返せるかも」と抱え続けてしまう。
この“心理的非対称性”が、損切り遅れや塩漬けを生む最大の要因です。
合理的な投資家であっても、感情を完全に排除することは不可能です。
だからこそ重要なのは、感情を排除することではなく、感情の存在を前提にルールを設けることなのです。
でもね、感情の存在を前提にルールを設けても、感情にはなかなか勝てないものなのです。今回だけは損切りのルールを破ろうという心理にFXをやった経験がある人なら一度ならず何度も経験していると思います。次回の投資のトリセツで詳しく検証しますが、おそらく、プロスペクト理論の逆の感情を持っているような人がまれにいて、このような特殊な感情を持っている人しか短期投資では勝てないというのが私の考えです。訓練によって、感情を克服するのは相当な困難を伴うと思います。実質無理。。
2. 群集心理(Herd Behavior)のメカニズム
投資の世界では、他人と同じ行動を取ることで安心を得ようとする傾向が見られます。
これを「群集心理」と呼びます。
バブル相場や暴落局面では、この心理が極端に働きます。
たとえばSNSやテレビで「この株が急騰中!」と報じられると、人は「自分も買わなければ」と感じる。
しかし、その時点ではすでに株価は割高で、リスクが高まっていることが多いのです。
逆に暴落局面では、「みんなが売っているから自分も売る」と動き、底値で手放してしまう。
このように、人は“他人の行動を基準に判断してしまう”傾向があり、合理的な判断を妨げます。
バブルの絶頂期には靴磨きの少年が投資の話をしていたという有名な話がありますよね。普段投資をしない身近な人が投資を始めようかなーと言っていたら危ないのかもしれませんね。
3. 感情を制する3つの投資ルール
① 感情より先にルールを決める
「5%下がったら売る」「20%上がったら一部利確する」といった明確なルールを事前に設定しておくことで、感情に流されにくくなります。
② 投資日誌をつける
自分がどんな感情でエントリー・利確・損切りをしたかを記録すると、思考パターンが客観的に見えるようになります。
私自身、FIREを目指した過程で投資日誌をつけ始めてから、焦りや後悔に気づけるようになり、判断の質が安定しました。
③ 客観的データに“感情の重み”を加える
チャートや財務データだけでなく、「市場がどう感じているか」を意識する。
つまり、数字だけでなく“人の心理”を読むこと。これこそが行動ファイナンスを活かす真の力です。
というのが、一般的な話になります。ですが、、私は、このような行動を取ったとしても人間としての感情の本質から逃げることは難しいと思います。よって、一般的な心理を持つ人は、特に損切りや利確という行動が必要となる短期や中期の投資で勝つことは不可能だと思います。
普通の人が投資で成功するには、長期で放置する投資をすることが必要なんだと私は思います。
4. 会計士が感じる「合理性の限界」
企業価値評価の現場でも、理論値と現実が乖離する場面は多くあります。
DCF法で計算した株価が割安でも、市場がそれを評価しない場合がある。
理由は単純で、「投資家の感情がまだ追いついていない」からです。
人は数字よりもストーリーで動きます。
だからこそ、会計士や投資家であっても“人間らしさ”を理解することが、合理性の限界を補う最も強力な手段なのです。DCF法による理論値なんて前提数値の条件や仮説の変動でいくらでも動きますからね。株価の理論値なんて絵に描いた餅です。
5. まとめ:感情を敵にせず、味方にする。感情が関係ない投資をする
投資の本質は、数字ではなく「人の心理」です。
感情を抑えようとするよりも、感情を理解し、ルールで包み込む。
この姿勢を持っても、短期投資や中期投資で、長期的に資産を守ることは難しいと思います。
普通の人が、投資で長期的に勝つには株式市場や事業の成長性を信じて長期投資を行い、感情を必要としない、つまり利益確定や損切りの必要がない長期放置の投資を行う必要があると私は思います。
行動ファイナンスを学ぶことは、単に理論を知ることではなく、
「自分の行動パターンを見つめ直す鏡を持つこと」。
投資も人生も、感情のマネジメントが成功の鍵です。感情に逆らう投資を行うべきではないのです。
次回は、「短期投資の心理戦 ― プロスペクト理論と反対の思考を持つ天才である必要性」をテーマに、
短期売買で勝ち続ける人たちがなぜ一般投資家と“逆”の行動を取るのかを深掘りします。