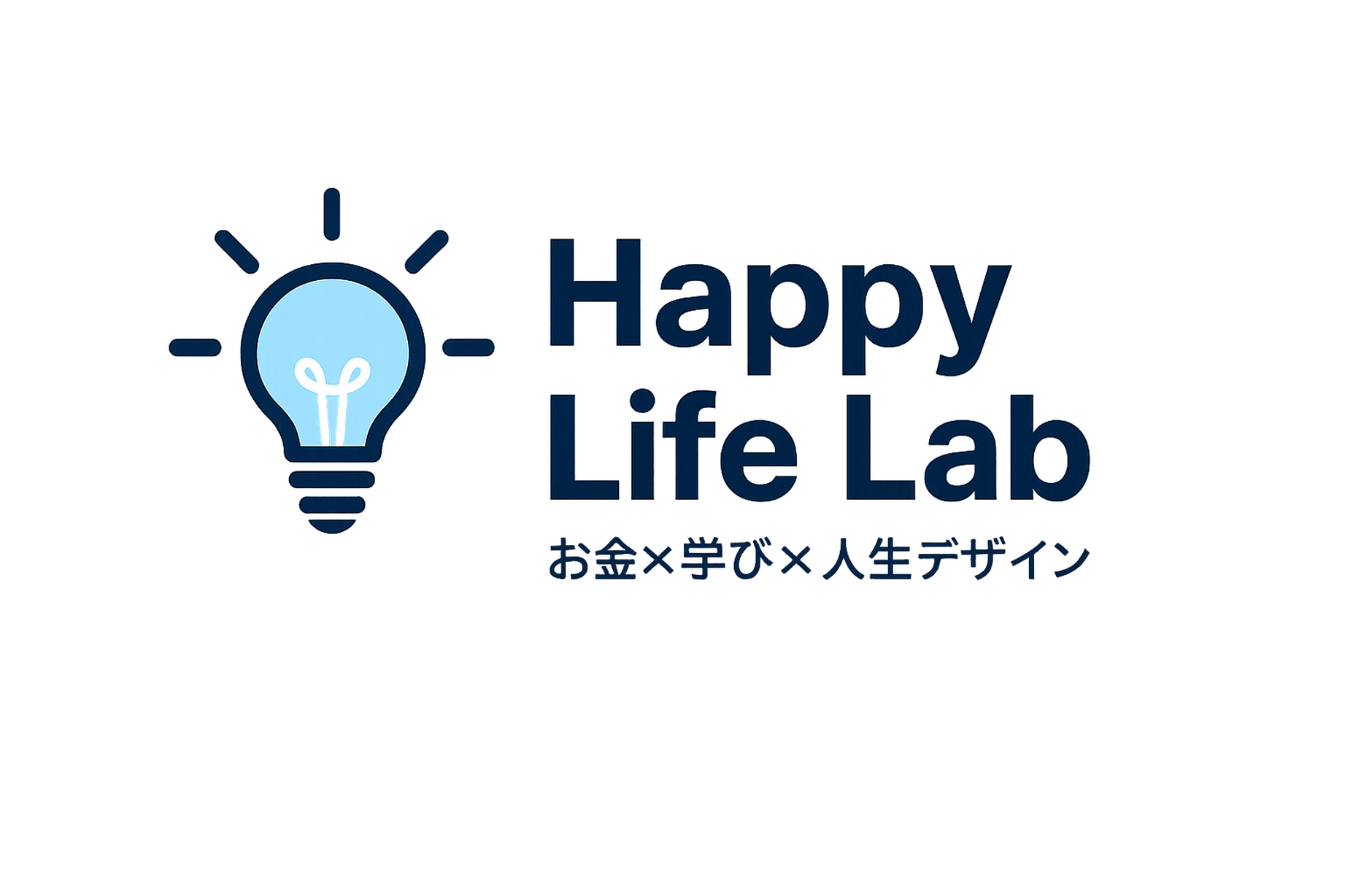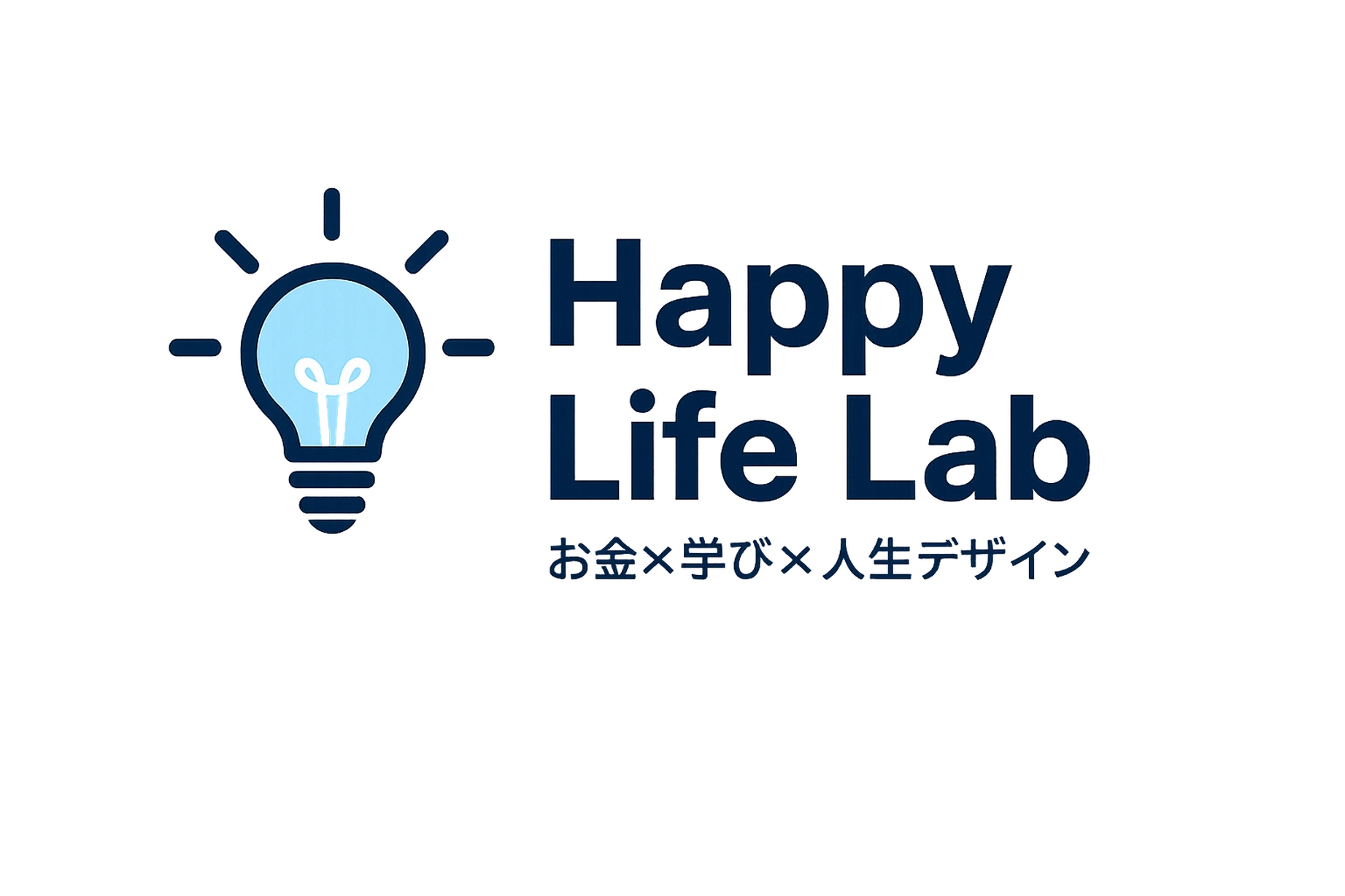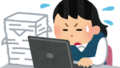フリーレントについて
前回、上場準備作業においてよくある会計処理修正で挙げたフリーレントについてですが、日本の一般に公正妥当と認められた会計基準にフリーレント期間分についても費用を按分表示しろと載っているわけではありません。IFRSの研究報告上(我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)-IAS第18号「収益」に照らした考察-)で貸主側については、フリーレント期間で収益を按分すべき旨が記載され、基本的には、これを根拠にして借主側の費用計上をフリーレント期間に費用按分するようになっていると思われます。
以下我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)-IAS第18号「収益」に照らした考察-の抜粋です。
『【ケース48:フリーレント期間がある場合の賃貸収入】
(a) 具体的事例
短期の不動産賃貸を行っている企業は、契約期間の当初数ヶ月間の賃料を無料としている場合がある。
このような取引において、契約総額を賃料の無料期間を含む契約期間にわたって均等に按分して収益を認識する場合と、契約期間から賃料の無料期間を控除した期間にわたって均等に按分して収益を認識する場合がある。
(b) 会計上の論点
・ 有料期間の賃料が適正な価格であると判断されるかどうかにより会計処理は異なるべきか。
・ 賃貸借契約の解約条項の有無により会計処理は異なるべきか。
(c) 実務上の論点
・ 賃貸借契約の解約の可能性について合理的な判断が困難な場合がある。
(d) 会計処理の考え方
短期の不動産の賃貸契約は、一般にオペレーティング・リース取引に該当するものと考えられる。我が国においては、オペレーティング・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことが求められている(企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」第15項)ため、原則として賃貸料を賃貸期間にわたり定額で収益として計上することになる。
我が国のオペレーティング・リース取引に関する会計実務では、解約の可能性が高い、又は相当程度の不確実性があると判断される場合を除き、契約総額をフリーレント期間を含む契約期間にわたって均等に按分して収益を認識している場合が多いと考えられる。これは、収益の総額は契約総額であり、その対価として提供する賃貸という役務は、フリーレント期間を含む契約期間にわたり均等に提供されているとの考え方に基づくものと考えられる。この会計処理は我が国の実現主義の考え方と整合的であると考えられる。
一方、解約の可能性が高い、又は相当程度の不確実性があると判断される場合には、将来の賃料収入の不確実性を考慮して、当該不確実性が解消されたと判断される時点、例えば本事例の場合でそのように判断されたとしたときには、一般的にはフリーレント期間経過時点からの残りの契約期間に応じて収益を計上することになると考えられる。』
おそらく、期間按分を要するタイプの賃借人のフリーレントは、賃貸借期間が定められておりこの期間の中途で、中途解約した場合にはフリーレント期間分の賃料の支払いが求められ、かつ中途解約の場合に残りの期間分の賃料の支払いが求められるタイプの契約であるタイプのフリーレントと思われます。これらの場合は、既に総支払額が実質的に確定しているので、それを賃貸借期間で均等按分して賃料として費用処理することが要請されるという思考になるからです。他方、中途解約した場合に、フリーレント期間分の賃料や中途解約後の期間分の賃料が不要なタイプの場合には、賃料総額が実質的に確定していないため、賃料の期間按分は不要であると思われます。フリーレントのある契約の罰則規定は色々な類型があると思われますが、実質的に賃料総額が確定していないタイプであれば、理論的には賃借人についてはおそらくすべて期間按分は不要と思われます。
なお、フリーレントの期間按分の会計処理は、通常の翌月分を前月に前払いをする契約の場合には、当初のフリーレント期間中や一部免除期間中については未払の賃料が発生し、賃料総額を賃貸借契約期間で除した月額賃料よりも毎月の支払額が上回る支払いが発生するようになると、その差額分についてフリーレント期間中に計上された未払の仕訳を取崩し、費用処理額と現預金額との差額として借方に未払が計上されることとなる。その後、当初計上した未払残高がゼロになった後は、借方の差額部分が未払ではなく前払いとして計上され、最終月はキャッシュアウトがないので、貸方に1か月分の前払い費用の取崩しが計上されて経過勘定がすべて無くなる処理となります。
また、フリーレントに絡む税務上の取り扱いですが、消費税法上の取り扱いは対価の支払いがないため、賃料の支払いに応じて課税仕入れを認識する、法人税法上は実質値引きとしフリーレント期間中は損金処理できないとする考え方と、法人税法上にて実質解約不能であり、発生主義で計上した会計上の費用をそのまま損金とし、消費税法30条1項の課税仕入れを行った期については、法人税の損金処理時点と一般に一致しておりいずれも発生主義にて税務調整不要で計上できるとする考え方があると思われる。明確に示した条文やタックスアンサーは出ていないようなので、税理士の見解に従うか、税務署に問い合わせて処理してもらうのが無難であると思われます。
資産除去債務の処理がなされていない
上場準備時のよくある修正、資産除去債務(ARO)についてですが、まず、監査法人の監査を受けている会社以外の会社は資産除去債務は計上していないですね!
個人的には、資産除去債務ってホントにいるのかなとも思います。 はっきりいって、かなり恣意性が介入する余地がありますし、基準上は、色々なケースがマニアックに載っていますが、実務上、基準にあるようなマニアックな処理ってなかなか適用できませんよね。会社によって色々なやり方で計上するのも比較可能性を阻害する要因にもなります。税務しか関係ない会社で、資産除去債務を計上すると、別表4でいたずらに調整項目が生じることになります。 そりゃ計上しないよねって感じです。資産除去債務とかフリーレントの期間按分とかいたずらに複雑化する会計処理は、個人的には好きではありません。
資産除去債務関係で注意する必要があるのは、一般に退去時期が確定していないため見積もれないので資産除去債務を計上しないという取り扱いは認められにくいという点です。通常は、過去の類似施設の退去実績を用いたり(平均や直近を利用など)、主要な設備の耐用年数を用いるケースがありますが、主要な設備の耐用年数と退去期間に因果関係はなく、税務上の耐用年数が到来したとしてもそのまま契約を継続することも多々あり、主要な設備の耐用年数を用いる方法は論理的ではないと思われます。
資産除去債務を計上する場合、①.敷金額と原状回復見込み額を比較して、敷金額よりも減少回復見込み額が大きな場合には簡便法は認められないと解される。②.①のような契約が存在する場合において、簡便法が適用できる物件に関する資産除去債務については簡便法を適用し、原則法と簡便法が混在することは会計処理の統一の問題ではないことから、簡便法と原則法を併用することが認められる。③.簡便法が適用できるケースにおいて原則法を適用することはかなりコスパが悪い。④資産除去債務計上額と実際の支出額との差額は、当該資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額と同じ区分に含めて計上(販管費に計上)することを原則であるが、当初の除去予定時期よりも著しく早期に除去することとなった場合等、当該差額が異常な原因により生じたものである場合には、特別損益として処理する(企業会計基準第 18 号資産除去債務に関する会計基準58項)。
税効果会計の不適用について
税効果会計の不適用ですが、中小企業の場合は、税務に則って会計も処理され、なるべく調整項目が発生しないようになっていることが多く、この点で、税効果会計も適用されていないことがほとんどとなります。
会計帳簿には、大きく分けると2つの側面があり、税務申告の基礎となる側面とそれ自体が株主やお金を貸している金融機関、その他利害関係者に会社の業績を公表するという側面があります。中小企業においては、主に税務申告の基礎となるという側面を重視して作成されるため、業績を適切に表示するという観点は、ほぼ無視されます。 そのため、税効果会計やその他の複雑な会計処理は無視されます。
ちなみに、金融機関は、会社が作成した会計帳簿をそのまま利用するのではなく、自ら必要に応じて適切に組み替えて業績の判断を行うため、借入にあたり、不良債権を費用処理せず貸借対照表にそのまま載せていても、金融機関の組替処理で費用処理されて評価されることになります。
税効果会計の具体的な注意点などは、別の記事にて詳細を記載したいと思います。