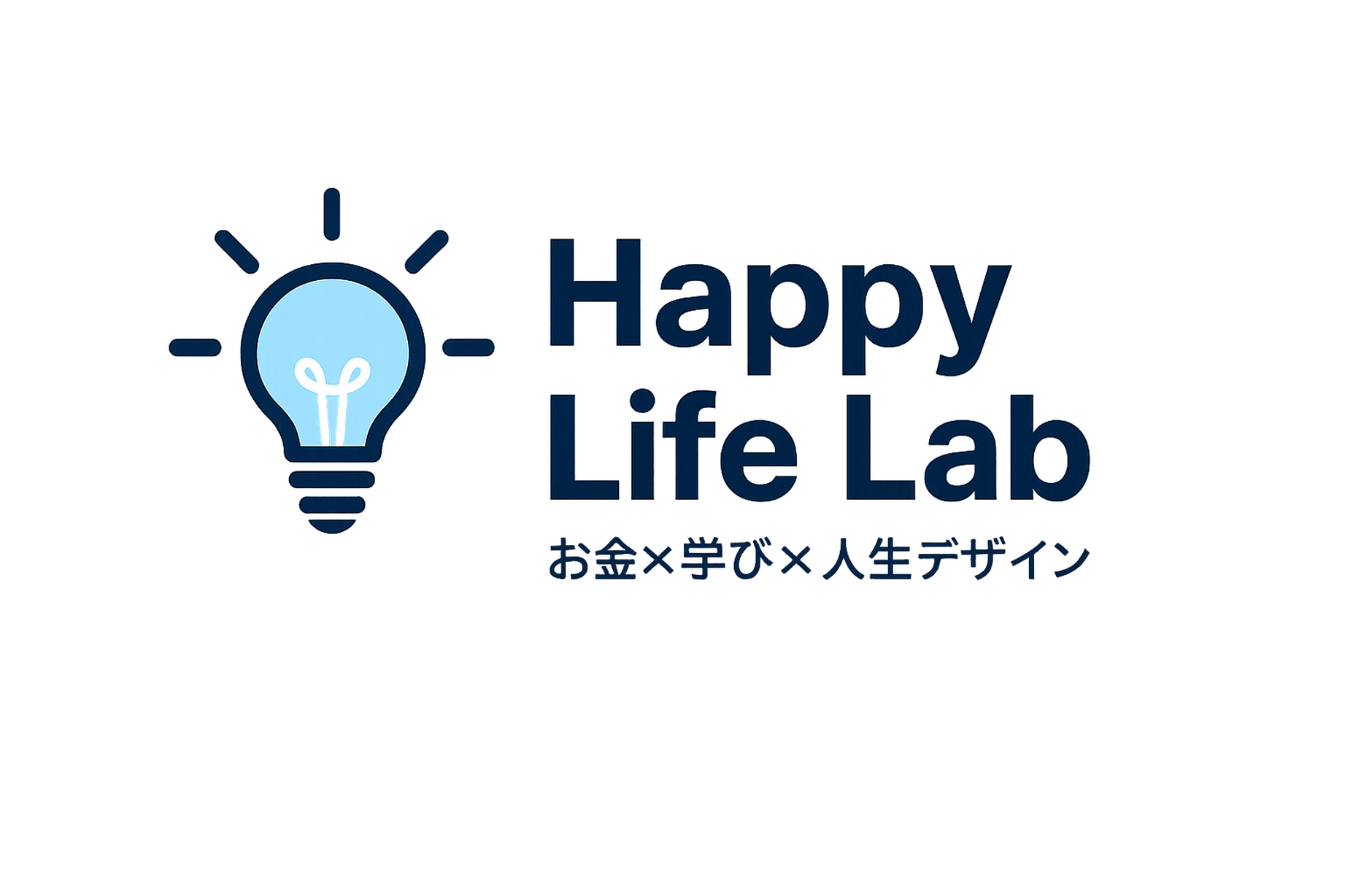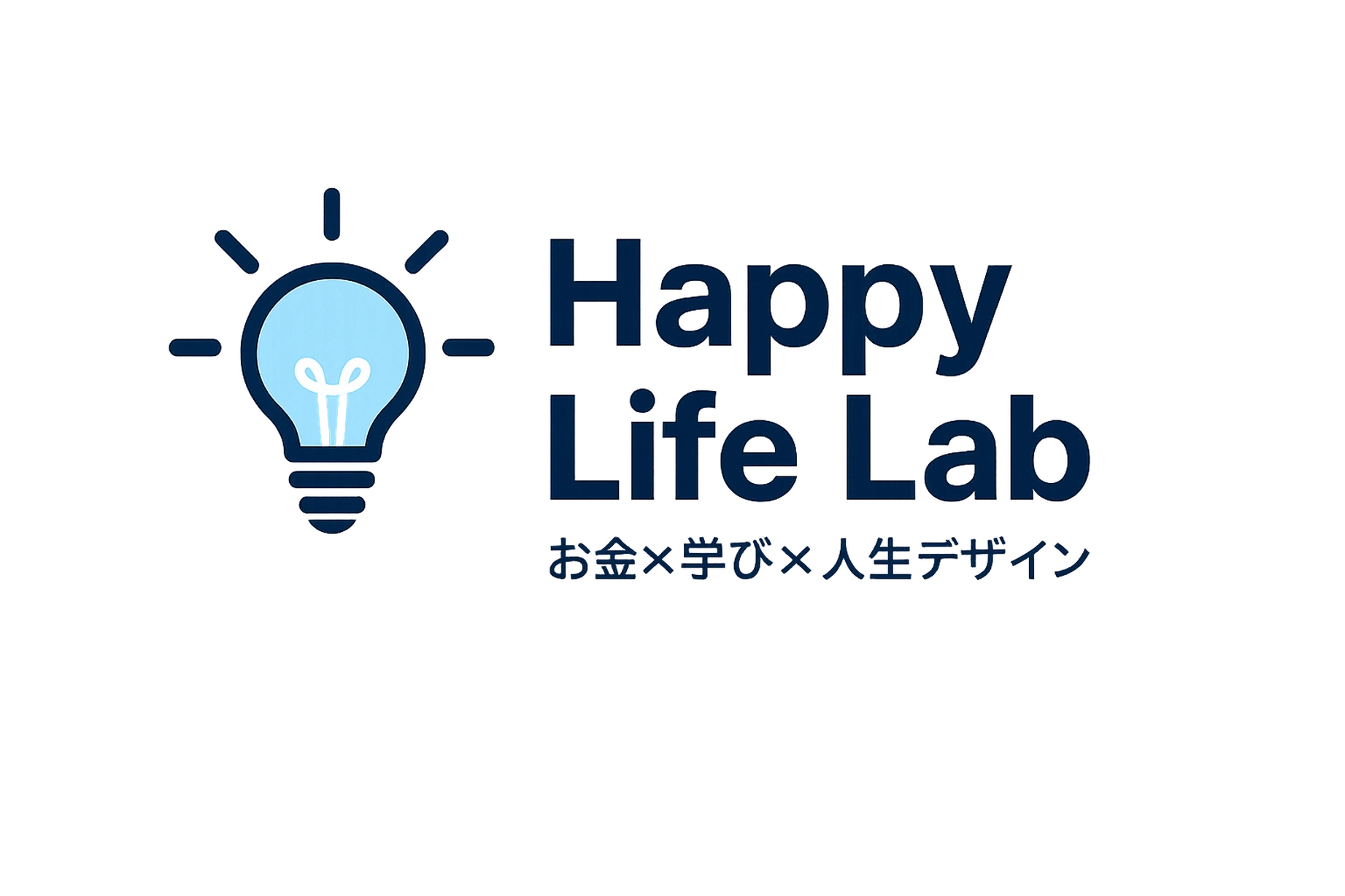IPO監査のトリセツ②|IPO準備における監査と経理体制の整備及び外注
上場審査を通すための基礎:監査法人選定・監査報酬・内部統制・月次決算
①IPO準備における監査と経理体制の整備
1. はじめに
企業がIPO(新規株式公開)を目指すとき、最初に直面するのは「夢の上場」よりも現実的な課題です。それが監査法人による監査対応と経理体制の強化です。どんなに優れたビジネスモデルや成長戦略があっても、財務や会計の基盤が弱ければ上場審査は通りません。IPOを推進するうえで「監査」と「経理」は車の両輪であり、どちらかが欠けると計画全体が頓挫してしまうのです。
特に日本では、金融商品取引法に基づく厳格な会計基準や内部統制報告制度が存在し、これに適合していない企業は上場を認められません。IPOの準備は、資金調達の夢を追いかける華やかな作業に見えますが、実際は地道で煩雑な経理の整備と監査法人との協議の積み重ねに支えられています。
ここからは、IPO準備企業が直面する監査法人の選定や経理体制の課題を掘り下げ、その重要性を整理していきます。
________________________________________
2. 監査法人の選定と現状の課題
(1) 大手から中小へのシフト
かつてIPOを目指す企業の多くは「四大監査法人(Big4)」と契約することを当然視していました。ブランド力や実績は確かに魅力ですが、IPO件数の増加に伴い大手の監査リソースは飽和状態に達しています。その結果、中小監査法人の存在感が急速に高まっているのが現状です。
現在のグロース市場(旧マザーズ)やスタンダード市場では、中小監査法人が主力となってIPO監査を担っており、特にスタートアップや中小企業にとっては現実的な選択肢となっています。IPOはリスクが高いため、大手の監査法人はコスパの悪いIPOを行わず中小監査法人は多少リスクを取ってでもクライアントを増やして規模を拡大したいという点から起きている事象ではないかと思われます。。本当は大手監査法人はコスパの良し悪しに関係なく、社会的なインフラとしてIPOをやらなければいけないのではないかというのが私の会計士として感じる部分ではあります。正直、きちんとした監査を行うとIPOは上場前、上場後しばらくは赤字となるのではないかと私は経験的に感じています。とすると、資金的な余裕がない中小の監査法人にIPOを適切に実施する体力はなく、本来的には中小監査法人がIPOをやるのは難しいのではないかと思います。特に、IPOはエラーを指摘して会社に直してもらう、不十分な管理体制を指摘して会社に十分な管理体制を構築してもらうなど、監査報酬を提供してもらっている得意先に対して、得意先が必ずしも直接的に望んでいない苦言を呈する必要があります。このようなことを行うには資金的な基盤、クライアント1社や2社なくなっても問題がないという余裕がある監査法人が行う必要があるのではないかと思います。
(2) 監査報酬の上昇
IPO準備が進むにつれて避けて通れないのが監査報酬の増加です。上場審査に耐えうる水準の監査を行うには、大量の証憑確認、契約書精査、実地調査などが必要であり、その工数は年を追うごとに膨らみます。特に収益認識や見積りに関する論点は追加手続が入りやすく、監査法人からの要求も増大する傾向にあります。結果として、監査費用は年々上昇し、IPO準備企業の大きな負担となっているのです。日本社会がインフレしている中で、監査報酬がステイというのは当然あり得ないし、監査報酬がステイしている中小監査法人は監査の品質が低下していると見られるべきであるとすら私は思います。実際、そんな状況が現在ありますよね。
(3) 監査法人から求められる「体制整備」
監査法人は単に「数字を確認する」だけではありません。経理部門の人員体制や内部統制そのものにも目を向けます。担当者が1~2名で手作業中心という体制では、監査法人の要求に応えられず、改善を迫られるケースが後を絶ちません。IPOを目指す企業は、監査法人の選定と同時に「自社の経理体制をどう強化するか」を真剣に検討する必要があります。会社に利益を生み出さない間接部門の人材を手厚くするには、以前に述べた会社オーナーのIPOへの覚悟が必須ですよね!
________________________________________
3. 経理体制整備の重要性
(1) 上場準備と経理人材の不足
スタートアップや中小企業では、顧問税理士任せであったり、経理担当者が1〜2名しかいないことも珍しくありません。その場合、業務は税務申告中心であり、月次決算も数か月遅れが当たり前です。しかし、IPO準備に入ると「スピード」「正確性」「透明性」が必須になります。小規模な経理体制では、監査法人の要求に応じきれないのが実情です。このような会社の利益に直結しない間接部門の増強には、IPOへの経営者の覚悟が求められます。また、後半で詳しく述べますがIPO後しばらくするとある程度落ち着いてきますから、その時に間接部門がオーバースペックとならないように、大手監査法人でIPOを経験している人材をIPOコンサルとして利用するなどで対応することも非常に有益な手段となると思います。IPOコンサルは個人のうでに依拠するので当たり外れはあるのでこの点が難しいところではあります。
(2) 上場審査に求められる水準
IPOを目指す段階では、以下のような体制が求められます。
• 月次決算を翌月10営業日以内に締められる体制
• 金融商品取引法に基づく会計基準での処理
• 職務分掌や承認フローを備えた内部統制
• 決算短信や有価証券報告書を作成できる体制
これらを満たすには、単なる「人員増加」だけでは不十分です。システム導入、業務フロー設計、内部牽制の仕組みが不可欠であり、経理を会社全体の戦略機能として捉える必要があります。
(3) 経理体制が遅れるとどうなるか
経理体制の整備が遅れると、監査法人からの指摘対応に追われて通常業務がおろそかになります。IPOスケジュールが後ろ倒しになり、資金調達や投資計画も狂ってしまうリスクがあります。実際、経理体制の未整備が原因でIPO計画を断念した企業も少なくありません。IPO準備の成功は、経理部門の人員数や人員の成熟度に大きく依存しているのです。
________________________________________
4. IPO準備における監査と経理体制の整備のまとめ
IPOを目指す企業にとって、監査法人の選定と経理体制整備は避けて通れない最重要課題です。
• 中小監査法人の活用が一般化しつつある
• 監査報酬は年々上昇し、体制整備が不可欠
• 経理のスピード・正確性・透明性がIPO成功のカギ
IPOは経営者や投資家の夢を叶える華やかなステージに見えますが、その裏では監査法人と経理部門が作り上げる地道な基盤が欠かせません。準備段階での体制整備こそが、IPO成功を左右する最大のポイントなのです。
監査対応を加速する仕組み化:資料標準化・承認フロー・月次早期化
②IPOコンサル活用の有効性と実務ポイント
1. IPOコンサル活用の有効性
(1) 専門家リソースの補完
IPO準備を進める企業にとって、経理・財務・内部統制を同時に強化するのは容易ではありません。多くのベンチャーや中小企業ではCFOをはじめとした上級財務人材が不足しており、日常業務をこなすのが精一杯というケースが一般的です。内部人材のみでIPOを乗り切れるくらい補充してしまうとIPOしばらくするとちょっと人員がオーバー気味になる可能性があります。成長著しい会社であればそのような可能性は少ないですが、ニッチ市場を主戦場としており利益率は高いけど成長性はそれほどではないという会社においてはそのような事態が発生しがちです。
そこで近年増えているのが「IPOコンサル」の活用です。公認会計士やIPO経験者が外部から参画し、内部で不足するノウハウや人材を補完することで、IPO準備のスピードと品質を高める狙いがあります。特に、自分が公認会計士であるというのもありますが、会計士ホルダーで大手の監査法人のIPO部門で5年~10年程度の経験を有する公認会計士は現場での経験が豊富で最もIPOコンサルに適している会計士であると思います。
IPOを目指すにあたり、少数の経理社員のみでは監査対応に苦慮しますが、IPOコンサルを導入してフローの標準化・月次決算の早期化を実現することにより、結果的に監査法人のレビューがスムーズになり、スケジュールの大幅短縮、コストの軽減につながるということが頻繁にあるのです。
(2) 業務効率化とコスト削減
以前は監査法人がある程度指導的な機能の延長で資料の作成などを手伝ってくれることもありましたが、現在は自己監査にならないよう監査法人が監査で求められる資料を作成するとこうことはほぼなくなりました。このような中で自社の社員のみで監査法人に求められる資料を作成しようとすると、不完全な資料の提出などにより必要以上に監査の追加手続きが発生し、監査報酬が想定以上に膨らむことがよくあります。
しかし、IPOコンサルが事前に資料を整理・分析し、監査法人の質問を先回りして準備できれば監査工数が大幅に減ります。
その結果、コスト削減だけでなく「IPO審査の遅延リスク」も抑えることができます。
(3) 「監査法人に好かれる会社」になるために
監査法人は、資料が体系的に整理され、質問への回答がスピーディーである企業を「監査しやすい会社」と評価します。こうした企業では追加の検証が減り、結果として監査報酬も抑制されます。
逆に、資料の不備や回答遅延が続く企業は「要注意先」とされ、監査の手続が増え、報酬や時間的コストが跳ね上がります。
IPOコンサルは、こうしたリスクを事前に潰し、監査法人からの信頼を高める役割を果たします。
________________________________________
2. 実務上のポイント
(1) 資料整理の標準化
IPO準備で重要な実務の一つとして「資料の整理」があげられます。監査法人は単に数値だけを見るのではなく、その裏付けとなる証憑資料を徹底的にチェックします。
そのため、以下のような仕組みを整えておく必要があります:
• 勘定科目ごとのファイルを作成し、契約書や請求書を体系的に保管する
• 会計システムの仕訳、仕訳入力の基礎となる証憑やExcelを体系的に管理する
• 第三者が見ても理解できるよう、各資料に簡潔な説明メモなどで誰が見ても理解できるようにする
実際、監査法人がストレスを感じるのは「毎回、同じ資料の読み方などを何度も聞かせざるを得ない」ケースなどです。標準化した資料管理を行うことや資料の内容をわかりやすく作ることは、監査法人の信頼を得る第一歩になります。これは同じ質問を何度もされることを回避するという観点から会社側の経理の人員のストレスにも当然になりますのでわかりやすい資料管理や資料作成はお互いにとってとても大事になります。
(2) 社内フローの明確化
経理体制を整えるうえでは、社内の承認フローや職務分掌を明確にすることが欠かせません。
• 入金・支払・承認のプロセスを文書化する
• 承認権限を役職ごとに明示する
こうした体制が不十分だと「不正リスク」や「内部統制の形骸化」といった指摘を受けやすくなります。
(3) 月次決算の早期化
IPO準備段階で最も大きな課題となるのが「月次決算のスピード」です。
未上場企業では月次が2〜3か月遅れどころか数か月遅れるということも珍しくありませんが、上場審査を通過するには 翌月10営業日程度での締めが求められます。
そのためには、以下の取り組みが有効です:
• 売上・仕入の計上ルールを月次で統一する
• 棚卸資産や経過勘定を年1回ではなく毎月処理する
• CFOや経理責任者を早期に採用し、部門の牽引役を配置する
これらが整わないと、監査法人から「決算の信頼性が低い」と判断され、IPOスケジュールが大幅に遅延する原因になります。
________________________________________
3. 失敗しやすい落とし穴と教訓
(1) Excelの属人化
多くのベンチャー企業がつまずくのは「Excelの属人化」です。取引の管理や会計処理の基礎資料としてExcelは便利ではあるものの、特にマクロやVBAを利用するスプレッドシートとして活用する場合には、作成者本人以外に変更できないということが発生します。これは、Excelの関数を使える人はかなり多いですが、マクロやVBAを使いこなせる人は関数を使える人に比べて大幅に少ないということに起因しています。Excelは可能な限り関数の利用までにして、VBAやマクロを使わずに、証跡管理やアクセス権限の制御が不十分にならないように注意が必要となります。
(2) 経理担当者の流動化リスク
IPO準備期は業務負担が急増するため、経理担当者が退職してしまうケースも少なくありません。
このとき業務が属人化していると、引き継ぎが滞り、決算や監査対応が麻痺する事態に直結します。
経理業務について日常業務、決算整理業務ともに「マニュアル化」と「チーム体制化」を意識しておくことが重要です。
(3) コストとスケジュールの見積もり甘さ
IPOにかかる監査報酬や体制構築コストを過小に見積もり、途中で資金繰りが逼迫する企業もあります。
「監査法人報酬+内部人件費+システム導入費」をあらかじめ数年分シミュレーションし、資金調達計画とリンクさせることが不可欠です。
________________________________________
4. まとめ・学びポイント
IPO準備における最大のハードルは「監査対応」と「経理体制整備」の二本柱です。
• IPOコンサルの活用 によって、内部リソース不足を補完し、監査法人との関係を円滑化できる
• 資料整理・承認フロー・月次決算の早期化 が、監査法人からの信頼獲得に直結する
• Excelの属人化 は大きなリスク要因となるため、マクロやVBAに頼ることないシステム化やマニュアル化が必須
最終的にIPOとは「企業が社会に対してどこまで説明責任を果たせるか」を問う場です。監査法人や投資家の視点に立ち、経理体制を客観的に磨き上げることが、IPO成功のカギとなります。
「自社の経理体制は、第三者に胸を張って見せられる状態にあるか?」を考えていただきたいと思います。
IPOは単なる通過点ではなく、持続的成長のためのスタート地点。その第一歩を誤らないためにも、監査と経理体制整備への真摯な取り組みが不可欠です。