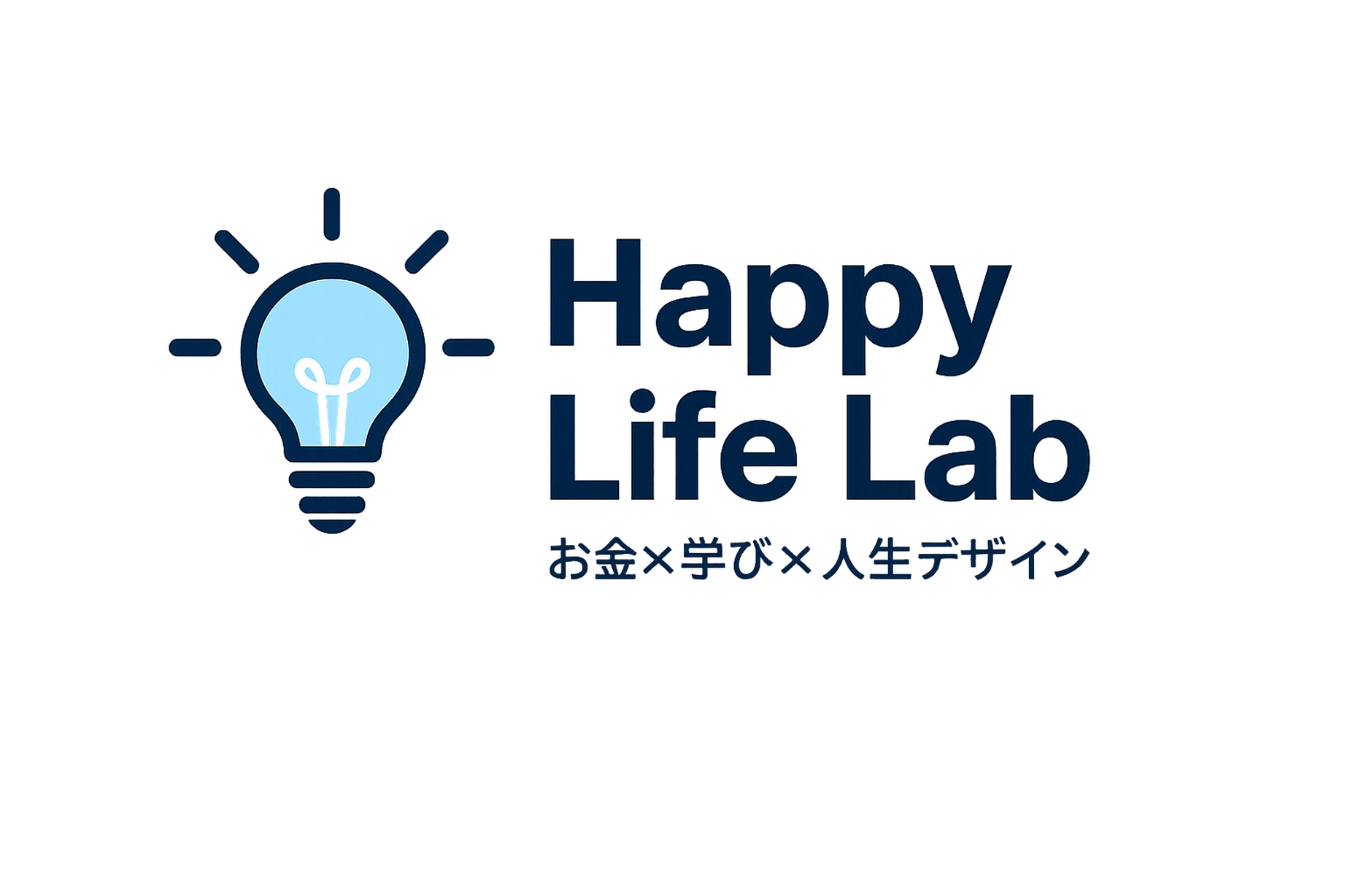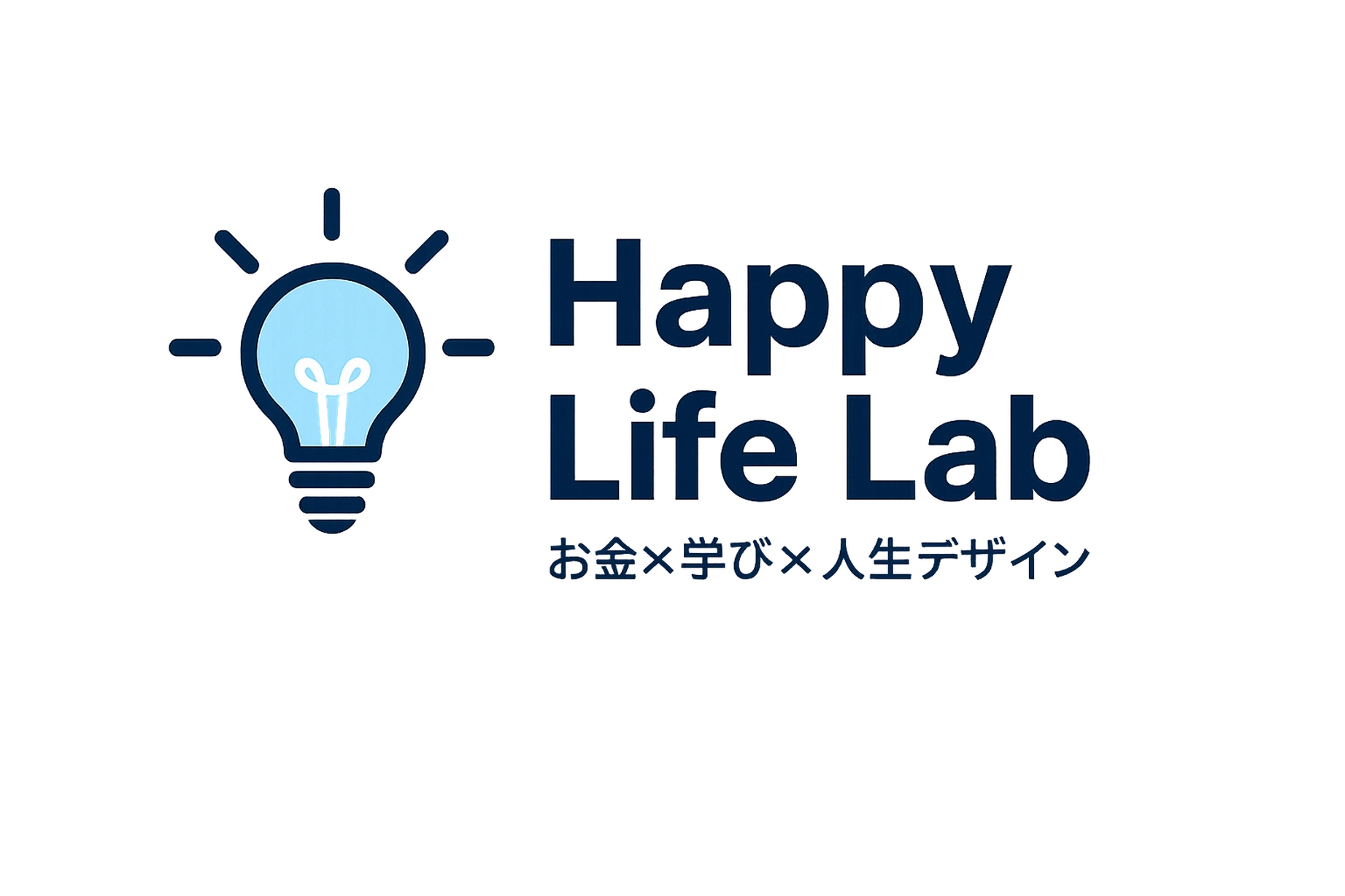IPO監査のトリセツ⑥|IPO準備でよくあるエラー④ 税効果会計と引当金、その他特殊項目の対応漏れ(前半)
1. なぜ税効果会計がIPO監査で問題になるのか
IPO準備企業が必ず直面する大きな論点のひとつが「税効果会計」です。未上場企業では「課税の公平」という名のもとに「法人税申告に耐えること」を主目的として会計処理が行われるため、税務と会計の差異を調整する「税効果会計」を採用していないケースがほぼすべてです。そもそも、非上場の会社では、決算書類を開示する必要もなく、税金計算を簡便に行う観点からすると税効果会計なんか適用する必要はありません。
ちなみに、企業会計上で計算された税引前当期純利益と税務会計(法人税法)上で計算された法人税等は対応しておらず、このズレを調整して利害関係者が求める適正な期間損益を把握できるように企業会計上で導入されたものが税効果会計です。言い換えると、貸借対照表に計上される未払法人税や損益計算書に計上される法人税等の科目は税務会計(法人税法)上で計算されたものであり、繰延税金資産や法人税等調整額は、これを会計上の数値に調整するために計上される科目であり、税法上の金額である未払法人税等と繰延税金資産をネットした数値が会計上の損益計算書上の数値となり、税法上の金額である法人税等と法人税等調整額をネットした数値が会計上の貸借対照表上の数値となります。なお、税金科目と税効果会計の科目はグロスで区分して表示されることになります。
しかしIPOでは、上場会社として世の中に公開して投資家の意思決定に資するために業績を適切に表示する財務諸表を作成することが前提とされます。したがって、会計基準に基づいた税効果会計の適用は必須となります。税効果会計を導入していないと上場はあり得ませんが、税効果会計を適用していない財務諸表は以下のような問題が生じます。
- 一時差異を放置し、当期利益が過大・過小に表示される
- 繰延税金資産や繰延税金負債が計上されず、純資産の姿が歪む
- 投資家の意思決定に資する会社の業績を適切に表した利益を表示できない
2. 繰延税金資産の計上漏れ
税効果会計を適用しない場合、最も大きなインパクトがあるのは繰延税金資産の計上漏れです。繰延税金資産とは、将来の課税所得から控除できる一時差異や繰越欠損金を、資産として計上するものです。
例えば、研究開発型ベンチャー企業では、赤字が数年続くことが多いですが、その赤字は将来の黒字と相殺できる可能性があります。しかし、繰延税金資産を計上しなければ、その将来価値は財務諸表に反映されません。結果として、現在の財務諸表の数値も将来の財務諸表の数値も歪めることになります。
3. 繰延税金資産の回収可能性判断の誤り
繰延税金資産を計上していても、その「回収可能性判断」が甘い場合、IPO審査で厳しく指摘されます。繰延税金資産は、その一時差異が解消する将来において利益が発生し、その期の税金を減少させる効果がある場合にのみ回収可能性があると判断できます。そのため、「回収可能性判断」が甘い場合には、回収可能性のない繰延税金資産が計上されてしまい、それはそれで財務諸表の数値を歪めることになってしまうのです。
典型的には以下のようなケースがみられます。
- 売上計画が過度に楽観的で、黒字化の裏付けが弱い
- 新規事業の収益予測を根拠にしているが、契約や市場実績が伴っていない
- 監査法人から「実現可能性に乏しい」と判断され、繰延税金資産の大幅取り崩しを迫られる
4. 引当金関連の未計上
税効果会計と並んでIPO監査で厳しく見られるのが「引当金の未計上」です。未上場段階の企業では、税務申告基準でしか処理していないケースが多く、課税の公平の観点から引当金の計上は限定的になります。そのため、以下のような引当金が未計上となっているケースが多いです。
- 貸倒引当金を税法繰入率でしか処理していない
- 賞与引当金を計上していない
- 退職給付引当金を計上していない
- 受注損失引当金や工事損失引当金の計上漏れ
6. 特殊項目の処理漏れ
税効果会計と引当金の次に問題となるのが、いわゆる「特殊項目」です。未上場企業では見過ごされがちですが、IPO審査では以下のような「特殊項目」は必ずチェックされて修正を求められます。
- 減損会計の適用漏れ
- 資産除去債務の未計上
- 未上場株式の評価損の計上漏れ
- フリーレント期間分への賃料の期間按分漏れ
- 返還されない礼金の償却漏れ
- 資産性のないのれん、特許権などの無形の固定資産を資産計上
- 資産性のない税法上の繰延資産の計上
IPO準備でよくあるエラー④ 税効果会計と引当金、その他特殊項目の対応漏れ(前半)(後半)
7. IPO監査で実際に指摘される典型パターン
IPO準備の現場で監査法人が実際に指摘した典型的な失敗事例を見てみましょう。
- 繰延税金資産の過大計上
あるITベンチャー企業は、将来の黒字化を前提に繰延税金資産を多額に計上していました。しかし、監査法人が事業計画の合理性を検証したところ、契約の裏付けが乏しく、売上予測に実現性がないと判断。結果、繰延税金資産の大半を取り崩すことになり、当期純利益が大幅に減額されました。IPO審査も延期に。 - 賞与引当金の未計上
製造業の企業では、賞与の支給を毎期行っていたにもかかわらず、当期の労務提供に基づく費用として計上していませんでした。また、本来確定しているものが引当金として計上されていたり、未払費用や未払金として計上されているものが本来未確定の引当金として計上されるべきであるという企業もありました。 - 退職給付引当金の放置
サービス業の企業が退職給付制度を整備していたにもかかわらず、将来の支払見込を負債として計上していませんでした。本来は長年に渡って徐々に計上されるものが、まったくの未計上であると一気にある年度で多額の退職給付引当金を一括計上する必要があり、その期は赤字になってしまうようなケースも発生し得ます。このような場合は、遡及修正の可能性も検討する必要があり複雑になります。 - 減損会計の適用漏れ
地方に展開した不採算店舗を閉鎖せず資産計上し続けた小売業のケース。会社は甘い計画を立てており、監査法人から「将来キャッシュフローで回収できない」と判断され、減損損失を計上し、これが数億円規模の損失となりIPO計画に支障をきたした。
9. 投資家から見た税効果会計の重要性
投資家は、企業の利益の「持続可能性」と「透明性」を最も重視します。税効果会計や引当金の誤りは、まさにこの2つを大きく毀損します。
- 利益の持続可能性
繰延税金資産の回収可能性がないのに計上している場合、その利益は実態のない「架空の数字」です。持続的な利益成長を示していないと判断されます。 - 利益の透明性
引当金や減損会計において、甘い見積りや甘い利益計画などに基づいて計上しており、実績値と大きく異なると「利益操作の可能性がある」とみられることもあります。結果として、企業価値評価においてディスカウント要因となる可能性があります。
10. 実務対応策(チェックリスト形式)
IPO準備企業が税効果会計や特殊項目でつまずかないために、実務対応を整理します。
1. 規程とマニュアルの整備
- 税効果会計方針を文書化し、経理部門で共有する
- 引当金(貸倒・賞与・退職給付)の計上ルールを規程に明記
- 減損会計・資産除去債務の検討フローをマニュアル化
2. 早期のシミュレーション
- 将来黒字化計画に基づく繰延税金資産の回収可能性を年次で検証
- 予実の乖離が続く場合は、回収可能性をの見積りにストレスをかける
- 早い段階で監査法人に相談し、判断基準をすり合わせる
3. 部門横断的な情報共有
- 人事部門と連携し、賞与・退職給付の支給実績を正確に把握
- 経営企画部門と連携し、事業計画の裏付けを強化
- 法務部門と連携し、契約上の撤去義務や訴訟リスクを洗い出す
11. 監査法人との関係強化
税効果会計や特殊項目は、判断に幅があるため監査法人とのコミュニケーションが不可欠です。
- 早期相談:不明点は期中から相談し、監査法人の判断基準を把握する
- 論点整理メモの作成:「論点→対応策→証拠資料」をまとめて提示
- 外部専門家の活用:税効果会計や会社に必要な特殊な会計処理に精通した外部専門家を採用
13. チェックリスト:税効果会計と特殊項目で失敗しないために
- 繰延税金資産の回収可能性を客観的に検証しているか
- 引当金を会計基準に基づいて網羅的に計上しているか
- 減損会計や資産除去債務を放置していないか
- 部門間の情報共有体制が整備されているか
- 監査法人との定期的なディスカッションを行っているか
- 外部専門家を活用して判断の妥当性を補強しているか
14. まとめ(後半)
税効果会計と引当金、特殊な会計項目の対応漏れは、IPO準備企業にとって最大級のリスクです。
- 繰延税金資産の過大計上や未計上は、利益水準を大きく歪めるとともに経理能力を疑われる
- 減損会計・資産除去債務の計上ミス、計上が必要な引当金の見積り誤りは質的に重要なエラーとなる
- 上記の修正がIPO直前になると、上場スケジュールへ影響するリスクが高まる
IPOを成功させる企業の共通点は「早期に論点を洗い出し、監査法人と共有し、保守的な会計処理を徹底している」点にあります。
税効果会計と引当金、特殊な会計項目の整備は、単なる会計処理ではなく「経営の透明性を示す投資家へのメッセージ」なのです。