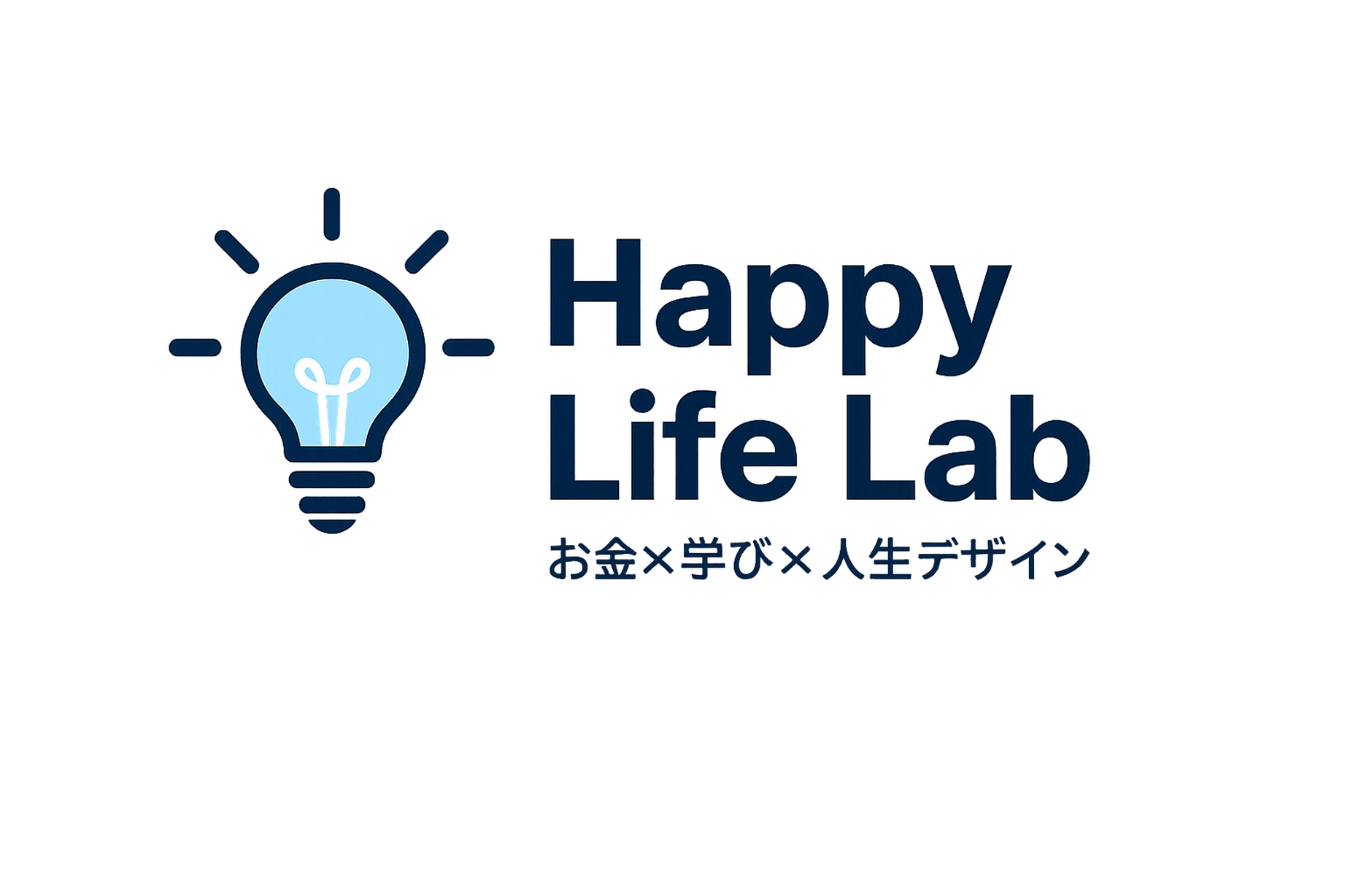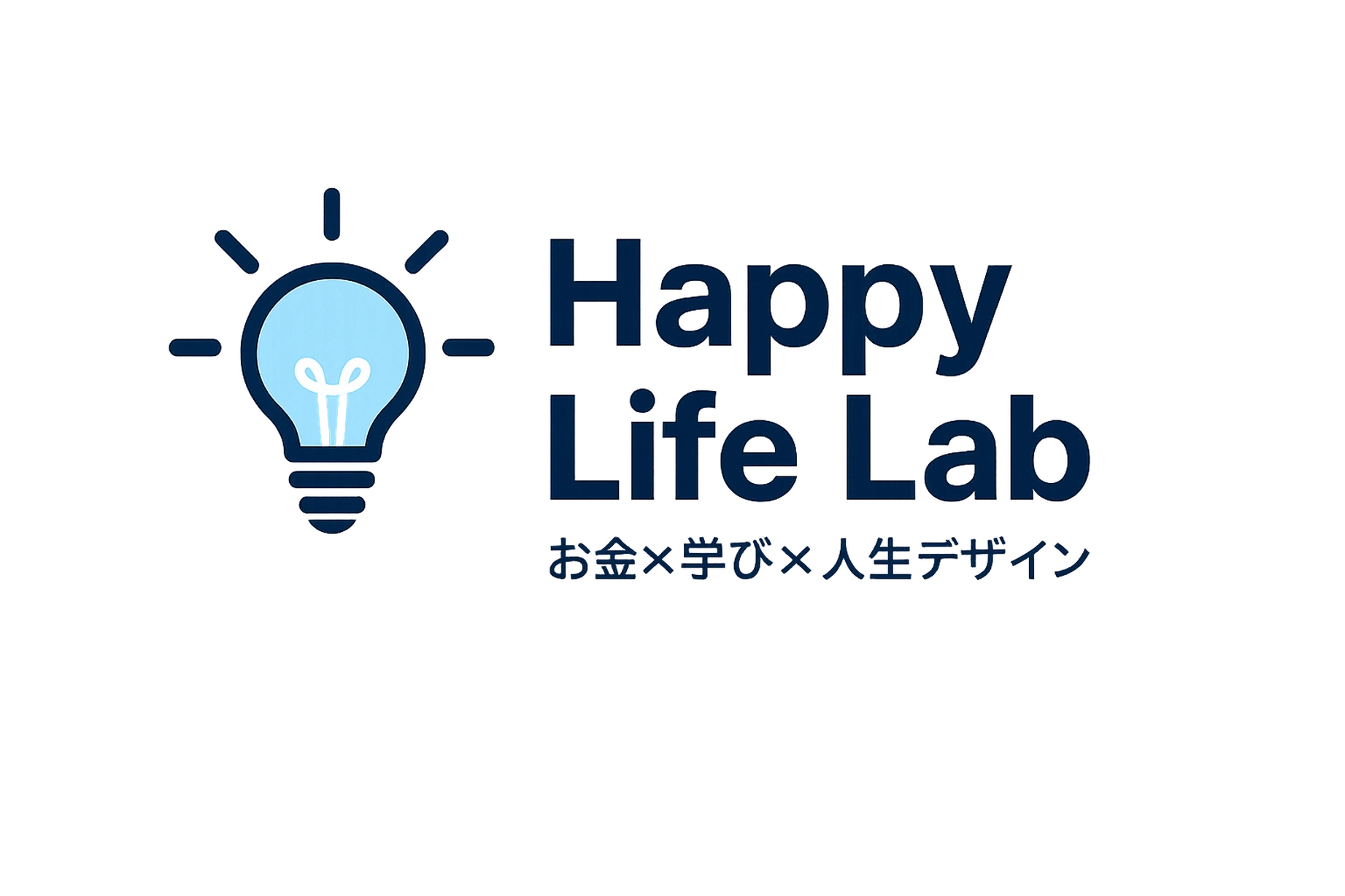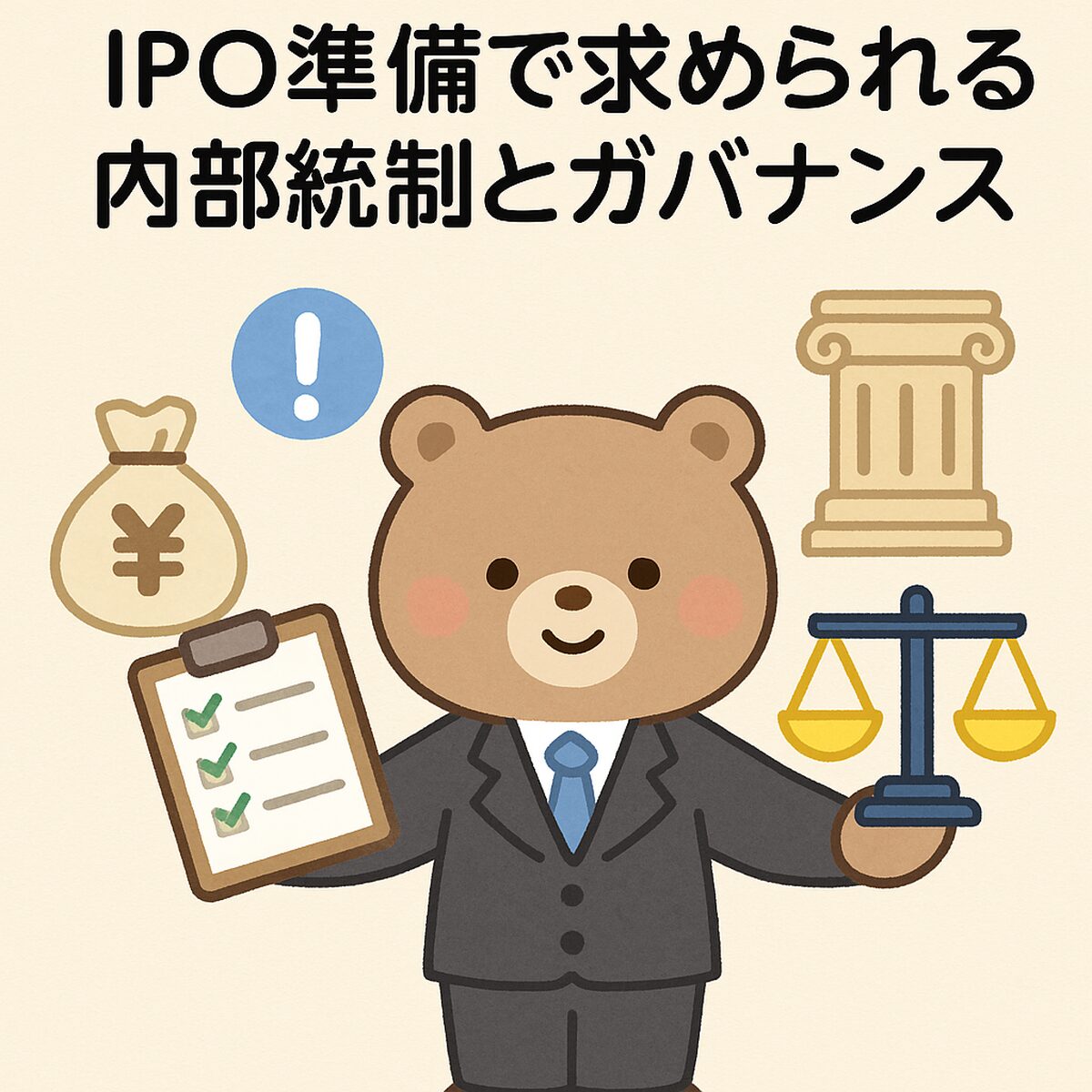IPO監査のトリセツ⑦|IPO準備で求められる内部統制とガバナンス(前半)
1. はじめに
IPOを目指す企業にとって「内部統制」と「ガバナンス(企業統治)」の整備は避けて通れません。監査法人や証券会社が最も重視するチェックポイントの一つであり、単に数値が正しいだけでは不十分です。その数値が「適切な仕組みのもとで作られているか」が問われます。
IPOは資金調達の場であると同時に「投資家保護」の観点から、企業の経営基盤の健全性が強く求められます。その中核を成すのが内部統制とガバナンスです。これらが不十分である場合、会計数値に信頼性があっても上場審査に通らないことすらあります。
また、内部統制・ガバナンスは一度整備すれば終わりではなく、継続的に改善し続けることが前提です。IPO後に成長する企業ほど、この仕組みが上手く回っており、投資家や市場の信頼を集めています。
2. 内部統制とは何か?
内部統制とは、会社の目的を達成するために社内に整えられたルールや仕組みを指します。米国のCOSOフレームワークや日本の金融商品取引法に基づくJ-SOX(内部統制報告制度)でも示されている通り、内部統制は「会計のため」だけの仕組みではなく、企業経営全般を律する枠組みです。
特にIPOでは以下の4つの目的が重視されます。
1. 業務の有効性と効率性:ムダなく成果を出せる仕組みか
2. 財務報告の信頼性:数字が正確で改ざんが防止されているか
3. 法令遵守:会社法・金融商品取引法・労務関連法令などを守っているか
4. 資産の保全:横領や不正利用を防止する仕組みがあるか
これらの目的は単独で機能するものではなく、組み合わせて初めて企業のリスク管理が実効性を持ちます。例えば、資産の保全が不十分であれば財務報告の信頼性も損なわれますし、法令遵守が欠ければガバナンス体制全体が形骸化してしまいます。
3. IPO審査で注目される内部統制の領域
IPO準備において、監査法人や証券会社が重点的にチェックするのは以下の領域です。
(1) 職務分掌と権限規程
経理担当者が仕訳を起こし、同じ人が承認も行う ―― このような体制は「不正リスクが高い」として必ず改善を求められます。
👉 入力者と承認者を分ける、二重チェックを導入するなど、牽制の仕組みが必須です。
特にオーナー企業では、社長や一部の幹部に権限が集中しがちです。しかしIPOでは「透明性」が重視されるため、組織的な意思決定やチェック体制がなければ評価が下がりますし、経営者が何ても自由に意思決定できる仕組みのままではそもそも上場できません。
(2) 資金管理
現金・預金は横領リスクが最も高い領域です。振込は二重承認制、出納は定期的な残高照合など、資金管理統制が整っているかどうかは必ず確認されます。
出納担当者による横領が発覚し、IPO計画が遅延した事例もあります。資金管理は「やっているつもり」「形式上のみやっている」では通用せず、運用実態と証跡が求められます。もちろん空チェックではダメです。
(3) 売上・債権管理
売上計上の基準が明文化されているか、与信管理ルールは存在するか、回収不能リスクに備えて債権管理表を作成しているか。これらはIPO審査で頻出のチェックポイントです。
特にスタートアップにありがちな「契約書なしの口頭取引」や「経営者の裁量での売上計上」などは大きなリスクとされ、改善が強く求められます。
(4) 在庫管理
実地棚卸のルール、帳簿残高との照合手続、棚卸差異の調整方法。ここが不十分だと利益操作が容易になってしまい、上場審査では必ず突っ込まれる部分です。
IPO監査の現場では「実在性が担保されているか」を重視するため、システム管理だけでなく、定期的な棚卸の実施が必要です。
(5) IT統制
クラウド会計やSaaSサービスを利用している場合、そのアクセス権限やログ管理の仕組みが整っているかも確認対象です。システム導入はスピードや効率を高めますが、権限管理が甘いと改ざんリスクが残ります。
内部統制の重要な焦点として、システム統制のチェックがあり、大手の監査法人などではITの専門家を利用して検証するケースがあります。
4. ガバナンス(企業統治)の整備
内部統制と並び、IPOで必須とされるのがガバナンス体制です。これは「経営の監督と牽制」の仕組みであり、健全な意思決定を裏付ける基盤です。特に、大きな不正は、経営者不正が多いことから経営者へのガバナンスがどう機能しているかというのは非常に重要になります。
(1) 取締役会の機能
形だけの取締役会は意味がありません。議事録を残し、実際に意思決定や監督機能が働いていることが重要です。IPO準備段階では、外部の視点を入れるために社外取締役の招聘が求められるケースも増えています。
取締役会が「社長の承認機関」にとどまっていれば、ガバナンスは機能していないと判断されます。経営戦略の議論、リスク管理の検討など、実質的に機能していることを証明する必要があります。そのため、取締役会では闊達な議論が行われ、これを議事録に残すことが重要となります。
(2) 監査役・監査等委員会
監査役が機能していないと「牽制機能が働いていない」と指摘されます。単なる形式ではなく、内部統制の不備を指摘できる体制が必須です。
特に上場企業では、監査役や監査等委員会が「経営陣に対してNoと言えるか」が試されています。監査役会の議事録や活動報告は、IPO審査で重要資料として確認されます。
個人的には、監査の実効性を確保するためには、社外監査役・社外監査等委員は、当該監査役の報酬以外に多めの報酬を持っていて、仮に監査役等の報酬が無くなっても痛くも痒くもないくらいの経済的な自立が必要ではないかと思います。
(3) 内部監査部門
IPO企業に必ず求められるのが内部監査です。社内ルールが守られているかを定期的に確認し、内部監査報告書を経営にフィードバックする仕組みが求められます。
「形だけの内部監査」を行いたがりがちな経営陣ですが、実質を伴わない内部監査を行う会社のリスクは非常に高いと監査法人は判断します。結果として、監査報酬が高くなったりするため経営者にとってもよくない結果となります。きちんと、内部監査に精通した人材を雇用して、年間監査計画を策定し、監査結果を経営会議や取締役会で報告し、経営陣が真摯に受け止めて改善につなげることが必要です。ここは、経営者の覚悟の有無が見えるところだと思います。覚悟がない経営者のもとではIPOが成功しない確率は上がります。
(4) コンプライアンス体制
内部通報制度、ハラスメント対応、情報セキュリティポリシーなど、法令遵守とリスク管理の仕組みも不可欠です。
IPO後は投資家や社会の監視が強まり、ここを怠ると企業価値が一気に毀損します。近年はESG投資や人的資本経営の観点からも、コンプライアンス体制は投資家評価の大きな要因になっています。
個人的には、経営者不正への最強のガバナンスが内部通報制度であると思います。監査法人は限られた人員、時間で行うものであり、経営者による隠ぺいを伴う不正を検出することは非常に難しく、経営者不正は、内部通報制度による内部通報で明らかになることがほとんどであると思います。
5. 前半まとめ
ここまで解説したように、IPO準備では「内部統制」と「ガバナンス」が極めて重要な審査項目です。ガバナンスは経営全体を統治するという内部統制よりも上位の概念であり、内部統制は「具体的な実行・運用」を担う「下位の概念」であると理解できます。
– ガバナンスは取締役会・監査役・内部監査・コンプライアンスなどで構成
– 内部統制は業務の有効性や健全性の確保・財務報告の信頼性の確保・法令遵守・資産の保全を図るための仕組み
この2つが整っていなければ、どれほど利益が出ていてもIPOにあたって取引所、証券会社、監査法人などから信頼が得られません。逆に、内部統制とガバナンスが機能していれば、IPO審査はスムーズに進むと思われます。利益の獲得と管理体制構築の両方がIPOにおいては必要になるのです。
IPO監査のトリセツ⑦|IPO準備で求められる内部統制とガバナンス(後半)
6. よくある不備と是正事例
IPO準備企業の内部統制・ガバナンスにおいて、監査法人や証券会社が繰り返し指摘する典型的な不備は以下の通りです。実際の現場で数多く見られる失敗事例を踏まえて整理します。
(1) 承認フローが口頭ベース
契約締結や経費精算を「口頭確認」で進めている会社はまだ多く存在します。しかしIPOでは「証跡として残っているか」が重要です。監査法人は**ワークフローシステムや電子稟議の有無**を確認し、口頭ベース運用は是正対象となります。
👉 **是正策**:電子承認ワークフローの導入、紙ベースなら承認印を必ず残すルール徹底。
(2) 経理担当者が一人で何でも処理
小規模企業では経理担当者が仕訳入力、承認、振込までを一人で行うケースがあります。これは「不正の温床」とされ、IPO準備では必ず改善を求められます。
👉 **是正策**:入力・承認・振込の役割分担。最低でも2人以上のチェック体制を敷く。
(3) 取締役会の形骸化
議事録は残しているが、実際には意思決定が社長一人でなされているケースもあります。これは「ガバナンスが機能していない」とみなされます。
👉 **是正策**:議題・決議事項を明確化し、外部専門家や社外取締役を招聘して実効性を担保。
(4) 内部監査の形だけ運用
内部監査を形式的に導入していても、年間計画が絵に描いた餅、実態を伴った監査が行われず形式的に資料を整えただけ、監査報告も経営層適切に共有されていないなどの例もあります。これでは「内部監査が機能していない」と指摘されます。
👉 **是正策**:実効性のある年間監査計画を作成し、実態を伴った監査を実施し、監査結果を必ず経営会議や取締役会で報告し、必要に応じて改善活動を実行する。
(5) コンプライアンス体制の未整備
内部通報窓口が存在せず、パワハラや情報漏洩が放置される企業はIPO審査で必ず問題視されます。
👉 **是正策**:外部窓口を含む内部通報制度の整備、ハラスメント研修の実施、セキュリティポリシー策定。
7. 実務対応のステップ
IPO準備における内部統制・ガバナンス整備は、以下のステップで進めると実効性が高まります。
(1) 現状把握
まず、監査法人や証券会社の指摘事項をリスト化し、現状の統制レベルを可視化します。Excelなどで「領域ごとの成熟度マトリクス」を作成すると、改善の優先順位をつけやすくなります.
(2) 整備計画の立案
IPOスケジュールから逆算し、「半年以内に整えるべき統制」「上場直前でも間に合う統制」を仕分けます。時間がかかるもの(システム導入、組織改編)は早めに着手する必要があります。
(3) 規程・マニュアルの整備
就業規則、稟議ルール、経理規程などをアップデートします。ポイントは「形式だけでなく、実務運用と一致しているか」。IPOでは「現場で実際に使われているか」を重視されます。
(4) 教育・浸透
ルールを作っただけでは不十分です。従業員向け研修やeラーニングを通じて社内に浸透させる必要があります。特に営業部門や管理部門の理解が浅いと、運用段階で必ず不備が出ます。
(5) モニタリングと改善
内部監査や社外取締役のレビューを通じて、運用状況を定期的に見直し、改善を繰り返します.
👉 内部統制は「PDCAサイクル」で回すことが不可欠です。
8. J-SOX(内部統制報告制度)との関係
IPO準備で内部統制を整備する際に避けて通れないのが「J-SOX(内部統制報告制度)」です。金融商品取引法で上場企業に義務づけられており、内部統制報告書を作成し、監査法人の保証を受ける必要があります.
J-SOX対応は負担が大きい一方で、IPO審査に直結するため、『早めに取り組むほど後が楽』です。特にシステム統制、職務分掌、決算プロセスの整備はIPO準備の序盤から着手すべき領域です。なお、既上場会社では、J-SOX制度というのは既に暗黙知としてある統制を洗い出して制度対応をする必要があることから必要悪のような制度と言われることがありますが、IPOを目指すような非上場会社においては、そもそも暗黙知としてのガバナンスや内部統制が存在しないことが多く、J-SOX対応というのは、IPOの会社にとっては非常に重要な仕組みであると思います。
上場後、3年間は監査法人の意見は免除されると制度変更がなされていますが、上場後すぐに監査法人の意見が必要とする制度に戻した方が良いとすら思っています。だって、IPOの会社ってここが一番ダメですからねー。。。
9. 監査法人・証券会社が重視する観点
IPO審査で監査法人や証券会社が最も注目するのは以下の点です.
– 内部統制の整備が形式的でなく実効性を持っているか
– ガバナンスが経営陣に対する「牽制機能」として働いているか
– 内部監査の指摘が経営に反映され、改善が回っているか
– 社外取締役・監査役が独立性を持ち、実際に発言しているか
– コンプライアンス違反のリスクを放置していないか
これらは「市場から信頼される会社かどうか」を判断する基準であり、単なる形式的整備では不十分です。
10. 成功する企業に共通する「浸透の仕組み」
内部統制・ガバナンスを形だけでなく「生きた仕組み」にするには、以下の工夫が効果的です。
– **社内ルールの掲示**:収益認識、承認ルール、稟議フローなどのルールを全従業員に対し常時閲覧可能な状態とする。
– **経営層からのメッセージ**:トップ自らがコンプライアンス遵守の重要性を定期的に発信。
– **評価制度との連動**:ルールを守ることが人事評価に反映される仕組み。
– **システム化による強制力**:承認なしでは処理が進まないワークフローをシステムに組み込む。
これらを通じて「内部統制は監査法人や外部者のためではなく、自社を守るためのもの」という意識を社員に浸透させることが、成功企業に共通する特徴です。また、内部統制は社内の人間をルールで縛ることになるためとても面倒でもあるので、経営者による旗振りもとても大事になります。
11. まとめ・学びポイント
IPOでは「数値の正しさ」だけではなく、「正しい仕組みで正しい数値が作られているか」が重要です。
IPOを成功させた企業は「内部統制とガバナンスを形式ではなく実務に落とし込み、改善サイクルを回している」点で共通しています。監査法人から「監査しやすい会社」と評価されることが、スケジュール短縮とコスト削減につながり、最終的に投資家の信頼獲得へと直結すると思われます。
はっきり言って、これまで見てきたIPOの会社で内部統制がバッチリで上場した会社って見たことありません。経営者には覚悟を持って内部統制をきちんと整えて欲しいものです。それが最終的には会社の利益の最大化、株主価値=基本的にはメイン株主である経営者利益の最大化にもつながるものであると私は信じています。