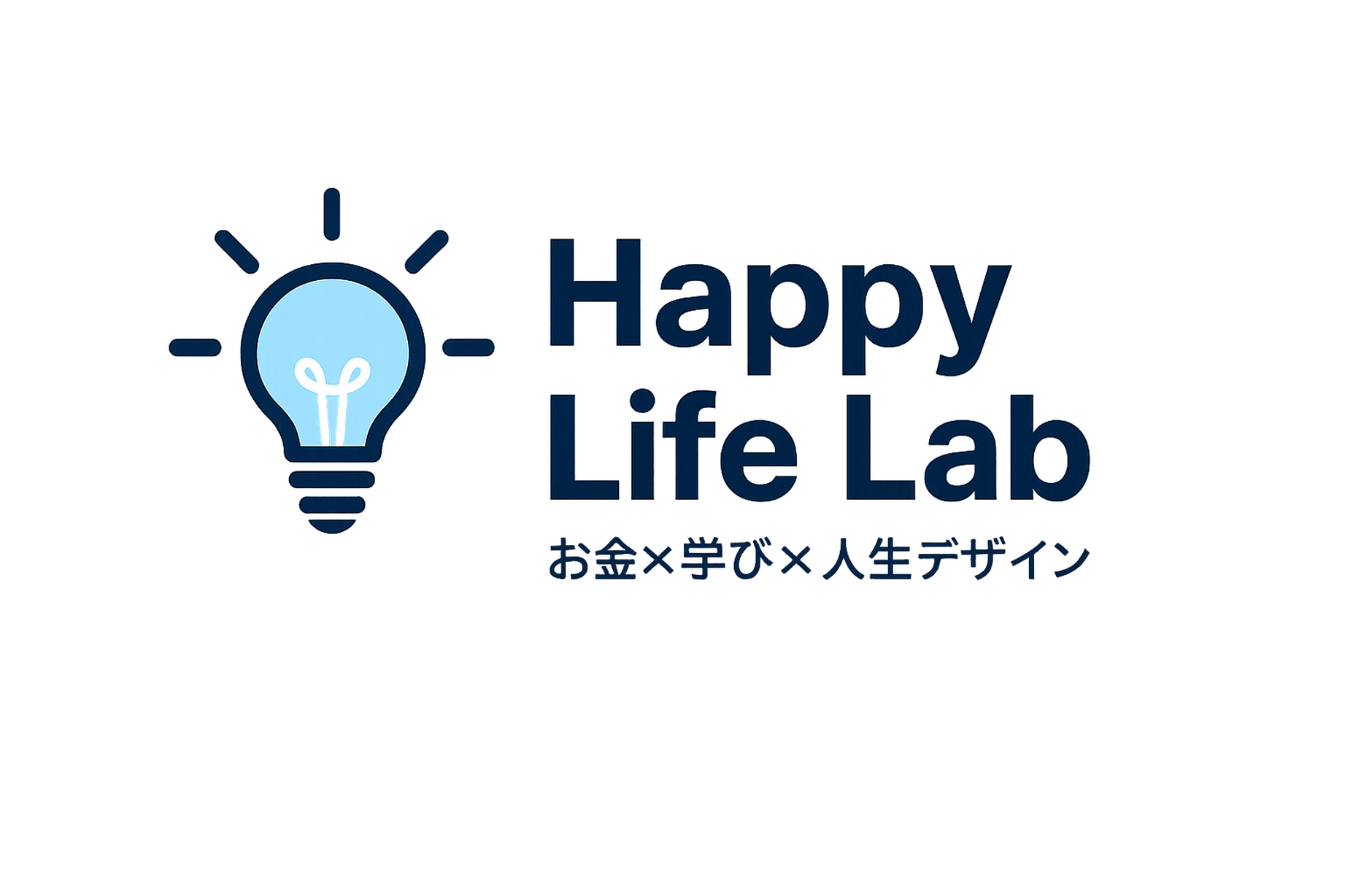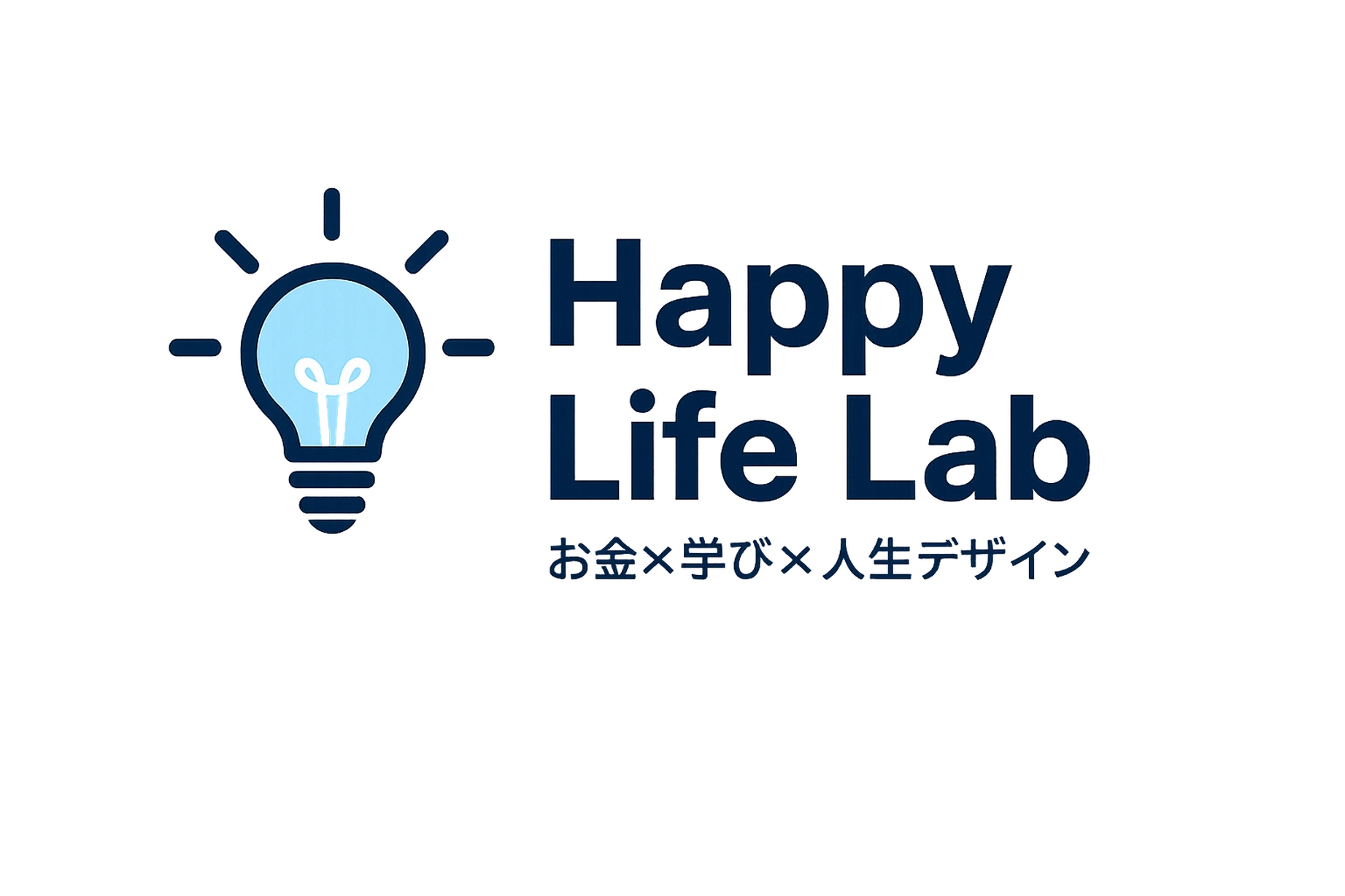こんにちは、Happy Master JOYです!FIRE(Financial Independence, Retire Early)を「夢」ではなく「設計」として捉え、シリーズで現実的に研究していきます。初回の今回は、FIREを実現・維持するための全体像を体系的に整理します。
FIREとは何か:働かないことではなく「選べる自由」
FIREの本質は、仕事をやめること自体ではありません。働かなくても生活が成り立つ状態=経済的独立(FI)を得た上で、働く・学ぶ・起業する・休むを自分で選べることにあります。実務的には「完全リタイア」よりも、時間や内容を選ぶセミリタイア(サイドFIRE)が現実解になりやすいと感じています。
私は基本的には、投資でお金を稼いで、仕事は自分の好きな仕事をマイナスにならなければ良いや的なスタンスでするのが人生を最もハッピーに生きる方法ではないかと思います。投資で時間をかけてしまっては、本末転倒になってしまうので投資は『長期×インデックス』をベースにすると良いのではと思います。投資が好きで、投資にスパイスを求めたい人は、『長期×テーマ個別株』を使うと飽きなくて良いのかなと思います。
投資で生活費を稼いで、趣味を仕事にするみたいな生活を送れたらHAPPYですよねー!
投資については、この投稿でおすすめ書籍やサイトを紹介しているので参考にしてね。
★公認会計士 JOYの資産運用おすすめサイト&本ランキング
FIREの構造:6つのレバーを並行設計する
FIREは単発のテクニックで達成されるものではなく、複数のレバー(てこ)を噛み合わせる構造設計です。本シリーズでは、次の6分野を基礎フレームとします。
① 自宅ローンレバレッジ(良質な負債の活用)
低金利・長期固定の住宅ローンは、初期の資産形成において「危険な借金」ではなく管理可能な資金調達になり得ます。インフレや賃金上昇局面では実質負債が目減りする側面も。とはいえ、返済負担を過度に背負うとキャッシュフローを圧迫するため、繰上返済の優先順位・生活防衛資金の確保を同時に設計します。なお、現在は金利上昇局面と言われていますが、変動金利より早く、既に固定金利が一定程度上がってしまっています。そのため、現在の固定金利で仮に借りたとしても返済ができるレベルの不動産を変動金利で借りることをお勧めします。
固定金利で借りた場合に返済可能な不動産を変動金利で購入すれば、差額分を投資に回すことにより、実質的に長期間返済する必要がないレバレッジを作ることができます。これこそが優良な負債であると言えるのではないでしょうか。仮に、大幅に金利が上昇するというような状況が起きた場合には、悪いインフレによる金利上昇などでない限り、投資している資産が高騰しているはずなので、換金をして一部早期返済を行うということも可能です。また、日本には住宅ローン控除という制度がありますから、ざっくり10年近くは残高×1%程度の還付を受けることができます。そのため、実質的な金利負担は大幅に軽減されます。これはすべて合法的な活用であり、このような国の制度は是非利用してください。
② 資産分散(通貨・地域・資産クラスの三次元)
FIRE後は取り崩しや配当収入が前提になるため、ボラティリティと為替影響に強い構造が必要です。通貨(円・ドルなど)/地域(日本・米国・新興国)/資産クラス(株・債・不動産・現金・金)の三次元で分散し、生活通貨と投資通貨を意識してずらすと、単一国・単一通貨リスクを抑えられます。
私は、そのためにAI投資を活用してAIによる強制的な分散を一部利用しています。正直アセットクラスの分散はリスクの分散に非常に有効と思いますが、難しいですよね。だからAIに委ねてます。特にFOLIOが有効だと私は考えておりFOLIOを利用しています。
また、近年はデジタルゴールドとしての一定の地位を築きつつあるビットコインなども有効だと思いますので、資産の一部にビットコインやイーサリアムなどを取り込むのも推奨できます。ただし、あくまでの一部にして、ここのウエイトを高くし過ぎないことが大事であると思います。私はコインチェックを利用して暗号資産を購入しています。
近年の日本相場では、株式に比べてJ-REITは割安と言われてますので、J-REITなどを組み入れるのも良いかと思います。リートは中リスク中リターンと言われていますので異なるアセットクラスの一部として組み入れるのは良いと思います。現物の不動産だとどうしても高額になりリスクが集中し過ぎてしまうので、リートはその観点からもおすすめです。
また、金兌換が停止されて以降、金の価格は紙幣が世界的にじゃぶじゃぶに刷られているのもあって、かなり好調です。今後もこの傾向は継続しそうなので、金を一定割合混ぜるのも有効であると思います。お金じゃぶじゃぶやる限り、金の価値は継続的に上昇するのだと思います。インフレに最も強そうですよね。
③ 複数アセット運用(守りと攻めの二層構造)
FIRE達成後も資産は運用し続ける前提です。私は以下の二層を基本にします。
- 守り層:現預金・短期債・ディフェンシブ資産(生活防衛資金3〜5年分を目安)
- 攻め層:世界株orS&P500や全米株インデックス+成長テーマ(長期保有でリバランス無し放置)
取り崩しは守り層から、景気後退時は攻め層の割合が自然に低下するなど、相場と生活のクッションを確保します。基本的には攻め層は放置が大原則です。
守り層のおすすめとしては、ネット証券で少しでも高金利の普通預金、債権タイプの投資信託(あまり長すぎない海外債権を対象としている投資信託が良いのかなと思っています。)、AI投資(私はFOLIOを利用しています)などがおすすめです。
攻め層としては、個人的にはAI革命が起きている最中なので、今からでもAI銘柄の個別株をサテライトで持つのは良いのかなと思います。ベースは自分は全世界株系よりもアメリカの成長の方が強いと思っているので全米系が良いのかなと。もうちょい尖ってNASDAQ100をベースにするとかもありかなーと思っています。
④ 収入最大化(労働時間に依存しないキャッシュフロー)
FIREは「無収入」を目指すものではなく、時間に縛られにくい収入源を増やす設計です。私の場合は、専門性を活かした講座・電子書籍・ブログ/YouTube、配当・不動産などの複線化によって、心理的安定と取り崩し率の低下を両立できれば良いなと思っています。
一般的には、自分の趣味などを仕事にして、赤字にならないように事業を行えれば、自分の人生としては充実するのではないでしょうか。一つだけ注意して欲しいのは、初期コストが大きいビジネスを行うことは推奨しません。失敗した時に取返しがつかなくなるからです。あくまでも、万が一失敗しても、自分の人生に大きなダメージはないなと言い切れる規模でビジネスは始めましょう。
小さく生んで、大きく育てるが基本です!
⑤ 節約・支出管理(固定費を増やさない設計)
支出は「見えないレバレッジ」。特に固定費(住居・通信・車・保険・サブスク)は一度上げると下げにくい。満足度の高い支出=残す/見栄・惰性の支出=削るという基準で、FIRE後も持続可能な生活コストを定義しておきます。
私は、マネーフォワードMEを使ってこの5年くらいの生活費がどの程度かかるものなのかを把握しています。実績ベースですし、ここはちょっと今後は削れるとか、教育費が徐々に増えてくるなどを加味して、現実的な出資額を管理します。一度増やした固定費はなかなか削れないので、自動車は少なくとも持たないようにして、使う場合はタクシーにしています。
今後も、固定的な支出はなるべく増やさずに、外食費や旅行費などを自分の財政状態に応じて変動させて贅沢費としてカウントしようと考えています。
⑥ 税務・制度活用(見えない支出を管理)
新NISAやiDeCoの活用、配当・譲渡の税制、国民健康保険や年金の取り扱いなど、制度設計を怠ると、税・社会保険でキャッシュフローが想定以上に削られることがあります。運用設計と同時に、制度上の最適化もルーティンに組み込みます。
新NISAやiDeCoの活用は当然として、iDeCoの取り崩し方や年金をいつからもらうかなどは、将来大きな影響を持つためシミュレーションを行った慎重な検討が必要になります。仮に住民税非課税世帯になれるのであれば、もらい方を工夫して住民税非課税世帯になると圧倒的にお得な老後が待っています。そういう制度になっているし合法的な方法なのです。
数値で考えるFIRE:取り崩し・安全利回り・寿命リスク
初期設計では、次の3点を最低限おさえます。
1) 取り崩し率の基準
一般に有名な「4%ルール」は目安にすぎません。インフレ・為替・税の影響を踏まえ、3〜4%の可変レンジで管理する方が実務的です。相場が好調な年は取り崩し率を下げ、悪い年は守り層から取り崩すなど、柔軟な運用ルールを定義します。最低限の生活費を把握するためにマネーフォワードMEなどのツールは非常に有効です。
2) 安全利回りの設定
長期平均の想定利回りからインフレ・税・手数料を差し引いた実質利回りで考えます。過去平均を鵜呑みにせず、控えめに設定して安全側で計画するのが基本です。なお、FIRE前には必ずモンテカルロシミュレーションなどを行って、自分がFIREしても問題ないのかの確認を行うことは必須です。
3) 寿命リスク(長生きリスク)
取り崩しの最大リスクは「長生きで資産が先に尽きる」こと。守り層の厚みと副収入の併用、そして支出ブレーキ(固定費を増やさない)が資産寿命を大きく延ばします。長生きリスクに一番強いのは公的年金であるのは間違いないです。公的年金+資産運用による利益で長生きリスクに備えましょう。
自宅ローン × FIREの共存:よくある疑問への私見
Q. 住宅ローンは完済してからFIREすべき?
ケースバイケース。金利が低く、返済比率が家計に無理のない範囲なら、完済を急がず並行で資産形成する選択肢もあり得ます。繰上返済は「流動性(現金クッション)を削らない範囲」で段階的に。この考えを遂行するのに一番大事なのは最初です。変動金利で買えるギリギリの家を買わないということが大事なのです。ギリギリの家を購入した人は余裕資金を良い負債を使ったレバレッジとして利用することにより、それほど大きなリスクを取ることなく投資資産を効率的に運用して資産を増やすことができます。
Q. 借入は怖い…
怖さの正体はキャッシュフロー不安です。固定金利・余裕の返済比率・防衛資金の確保の3点が満たされていれば、ローンはコントロール可能な金融ツールと捉えられます。最初が肝心なのです。自分の財政状態や支出状況、収入状況に対して多すぎる借入金のボリュームは怖いです。高すぎない家を多すぎない借入金で購入した場合には、借金はそれほど怖くないのです。
今日からできるミニチェックリスト
- 生活防衛資金は生活費3〜12か月分を確保しているか
- 固定費(住居・通信・車・保険・サブスク)を年1回見直しているか
- 投資は通貨・地域・資産クラスの三次元で分散しているか
- 副収入(配当・不動産・コンテンツ収入など)を一本以上持っているか
- 新NISA・iDeCo・税・社会保険の制度周りを押さえているか
まとめ:FIREは「静かな構造改革」
FIREは資産を増やすゲームではなく、人生のキャッシュフローを設計するプロジェクトです。自宅ローンを敵にせず、複数アセットで備え、支出を制御し、収入を分散する。これらを年単位で静かに積み上げることが、実現と維持の鍵だと考えています。
次回以降では、ここで示した全体像のうちのそれぞれのテーマを掘り下げます。お楽しみに!
※改めて:本記事は情報提供を目的とするもので、投資助言ではありません。具体的な投資・運用判断はご自身の責任でお願いします。